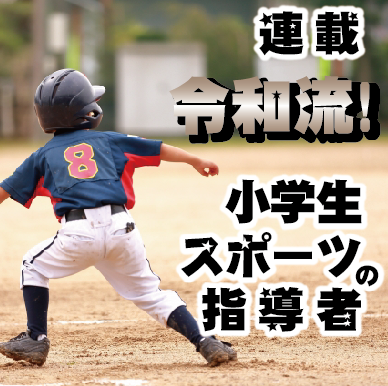
本職:経営コンサルタント・弁理士・人材育成・人間関係メンター。
この4月から:少年野球のコーチ。
全ての経験を通じて、現代の『最も理想とする小学生スポーツの指導』について、連載をしたいと考えています。
答えではなく問題提起です。
小学生のスポーツの指導に携わる方々、保護者の皆様に、問題提起をさせていただき、最終的なゴールは、スポーツに取り組む全ての小学生の方々に、健全なスポーツの環境を指導者皆様、保護者皆様と築き上げられたら幸いです。
第1話、第2話ともに、少しネガティブな内容になったかもしれません。パワハラから脱却することと、上下関係を強いることを止めること、これらは、指導者として健全な指導を行うために、まずは『入口』として不可欠です。
ですので、まず第1話、第2話にご納得いただいてから、こちらの第3話を読み進めてください。
『「メンタルの強さ」は「技術」よりも大切?!』
という内容です。
スポーツのスキルを分解すると・・・
- 目指す最高の結果を出すための身体の動きを身に付けて、
- 試合や大会でのシーン・シーンで、状況判断をして、
- 身に付いている身体の動きを、思った通りに実行する
スポーツは違っても、上記3つに分解できるのではないでしょうか。
技術と状況判断だけで、選手は大会や試合で活躍できる?
日頃の練習、レッスンでは、上記のうち、特に「1」、そして「2」を重点的に磨いていくものと考えます。
(「2」の状況判断の能力については、普通の練習だけではしっかり磨き切れません。それはまた別の時に後述します)
しかし、練習では完璧だったはずが、試合や大会では、思っていた通りのパフォーマンスを発揮できなかった、これは、よくあることだと思います。
野球で考えれば、バッティング練習では、長打を連発していたのに、いざ試合では、全打席、三振かショートゴロ、ということですね。
つまり、スポーツのスキルのうち、「1技術力」と「2状況判断能力」を磨いても、「3正確な実行力」が不足すると、試合や大会では、ほとんど活躍できません。
こういう掛け算が成立するのではないでしょうか。
発揮するチカラ = (技術力 + 状況判断能力) × 正確な実行力
技術力や状況判断能力がいくら、100%に近くても、「正確な実行力」が20%などだと、この掛け算の通り、総合的に20%にしかならないのです。
この「正確な実行力」は言い換えると、
『メンタルの強さ』
です。
スポーツにおいて、技術力や状況判断能力と同等、もしくはそれ以上に必要だと私が考えるのが、『メンタルの強さ』(メンタルタフネス、などとも言いますね)です。
メンタルの強さを強化・維持するためには・・・?
これは、試合や大会の『場数』はもちろん大切です。誰でも、初めて出場する試合や大会は、極度に緊張し、メンタルの強さは保てず、ベストなパフォーマンスは出せないことが多いでしょう。
かと言って、場数のために、試合ばかりを設けると、逆に、「1技術力」は、あまり磨かれないので、当然活躍もできず、自信を失い、メンタルをどんどん弱めかねません。
メンタルの強さを磨くためには、日ごろの練習から、指導者は意識をしていく必要があります。
メンタルの強さを強化・維持するために、もっとも大切なのは、
『選手の自己肯定感や自信』
です。
試合や大会の、『土壇場』で、本来であれば極度の緊張で押しつぶされてしまいそうなシーン。
このシーンで、唯一頼れるのは、『自分はここで力を発揮できるはずだ』という自分自身への信頼(自己肯定感)、強い自信です。
この自己肯定感や自信が弱い選手は、土壇場で、『自分は失敗してしまうんじゃないか』と悪いイメージを膨らませやすいです。
そうすると、そういうイメージは、実際の結果も、悪い方向へ引っ張ってしまいます。
『自己肯定感や自信』
これが、メンタルの強さに、最も重要な要素だと考えます。
、『メンタルの強さを鍛えるのが、一番難しいんだよ・・・』と現場に携わっている指導者のかたは、お思いになるかもしれませんが、意外と、日ごろの練習での小さな努力と働きかけで、メンタルの強さは、少しずつ高めていくことが可能だと考えます。
指導者のどういう指導で、高められるか
先ほど書いたように、『選手の自己肯定感や自信』は、どうやったら、指導者として少しでも伸ばしてあげられるか、を常に頭から離さないで、言葉を選ぶこと、小さな選手の変化を見逃さないこと、これが『メンタルの強い選手たちを育てる』方法だと考えます。
そのために、具体的には、以下のような働きかけを、出来ますでしょうか。
- 選手がミスしたときに、「何をやっているんだ!」と、ミスしたこと自体を責めることをしない
- ミスや未習得スキルに対して、具体的な改善をレクチャーできるときは、伝える。たまたまのミスの場合、気持ちを切り替えさせる
- そして、次はミスが少しでも減ったとき、そのミスを減らせたことを見逃さずに、具体的な言葉にして褒める
- 結果だけで、選手にフィードバックをしない。選手の具体的なチャレンジ、工夫、努力を必ず見つけて、そこを具体的に褒める
- 「ばか」「ドジ」「下手」などの、自己肯定感を低める言葉をぶつけない。自分はやれば出来るんだ、というイメージを持たせる言葉をかけ続ける
- 選手がスランプのときは、規定通りの距離やルールではなく、もっとルールを緩和してあげて、まずは成功できるイメージを取り戻させてあげる。それから少しずつ規定通りの距離やルールに戻していく
上記は練習でも試合・大会中も、同様です。とにかく「自己肯定感や自信」が強い選手は、『メンタルの強さ』を発揮して、試合や大会で、能力通りに、もしくは能力以上に、活躍できる可能性が高くなります。
ちょっとした接し方の改善で、簡単にできる『メンタルトレーニング』なので、実践してみていただければ幸いです。
執筆:田村恭佑
(人間関係メンター×弁理士×経営コンサル)