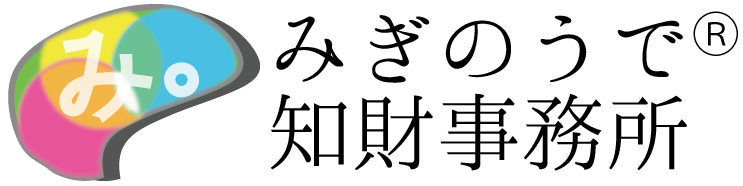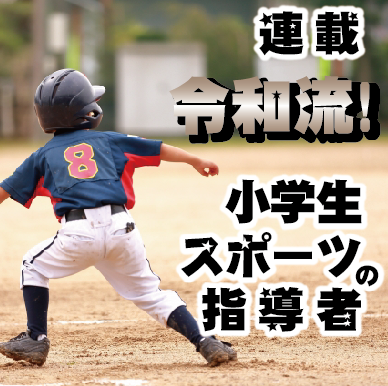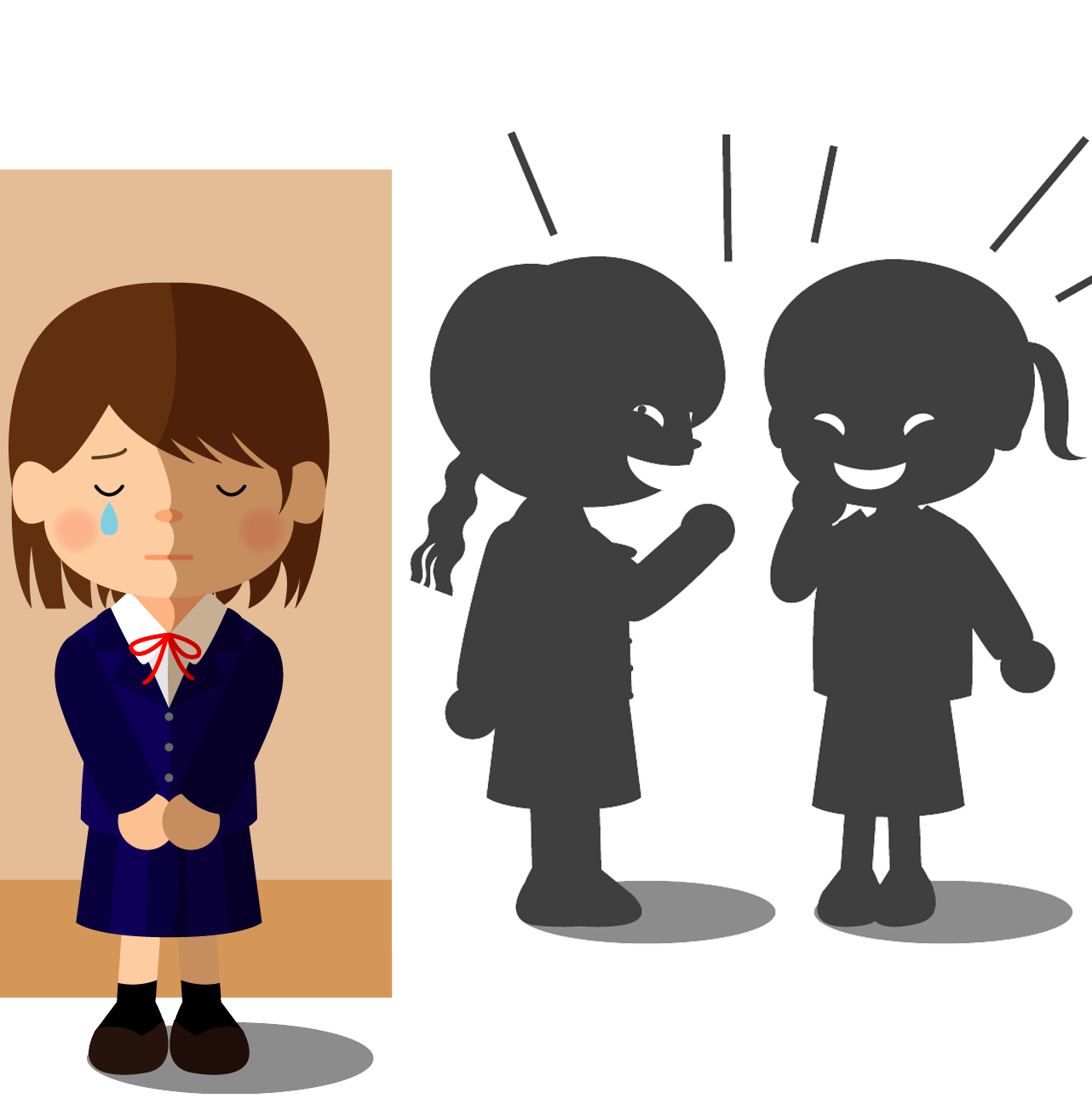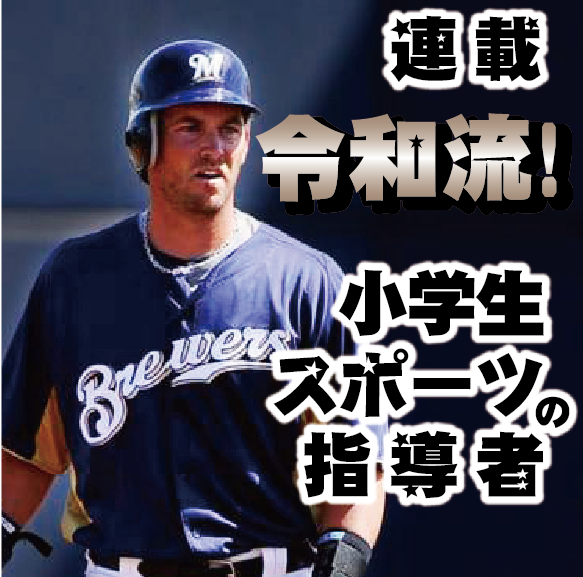小学生のスポーツの指導に携わる方々、保護者の皆様に、問題提起をさせていただき、最終的なゴールは、スポーツに取り組む全ての小学生の方々に、健全なスポーツの環境を指導者皆様、保護者皆様と築き上げられたら幸いです。
第1話 『パワハラしないと、強いチームにならないの?』
第2話 『指導者と選手は”対等”と強く意識しよう』
第3話 『メンタルの強さは、技術よりも大切』
第4話 『チームと個人。どちらに重きを?』
第5話 『大谷翔平選手の新打撃コーチの方針に学ぶ』
第6話 『指導時の腕組み、サングラス、呼び捨てについて』
今回の第7話は、『スポーツ指導では、精神的ストレスをかけたほうが、強い選手に育つ??』という内容です。
大別すると二極化する現代のスポーツ指導
民間企業や公的機関などの職場では、”ブラック組織”と揶揄(やゆ)されてしまうほど、今や”パワハラ”組織は、すっかり減ってきましたし、仮に存在したとしても、表立って外部にばれるような形では、パワハラがまかり通らなくなりました。
(ハラスメントに関する記事『1回きりのハラスメントでも命取りの3つの理由』)
しかし、スポーツ指導となると、コーチ自身の職場では完全にタブーとされていることが頭から離れてしまい、現代でも根強く、以下のような指導が残存しているのが現状です。
- 選手がミスをすると、罵倒してミスを責める
- 選手の一挙手一投足に対してダメ出しをする
- 少しでも元気のない選手がいると罵声を浴びせられる
- 1人のミスに対して延々に練習を終わらせないという体罰練習
- 連帯責任を逆手にとった、罰則的な指導
- 選手に対して「馬鹿、下手、死ね」などのおとしめる言葉がけ
- 他の習い事で練習を休む選手に対して『アイツはサボっているダメなヤツだ』と平気で表現する
一方で、様々なスポーツ記事で、『小学生や中学生の誤ったスポーツ指導』が取り立てられており、昨今は、以下のような(民間の職場などでは当たり前ですが)スポーツ指導を採用するケースが少しずつ見え始めています。(参考記事:『「勝つことは二の次」野球離れストップへ、変わる指導法』、『ブラック寸前? 少年野球の現場で悩む父親ライターの正直な報告』)
- 罵声禁止
- 非認知能力の向上を目指す指導(自己肯定感、自信などを高める)
- 体罰や罰則を用いる練習の禁止
- 勝利至上主義からの脱却、そのスポーツを楽しむ土壌作り
つまり、現代のスポーツ指導は、大別すると以下の通り二極化しています。
- パワハラ、体罰を辞さない高圧的指導
- 選手の気持ちや成長を尊重する選手主導指導
高圧指導者の言い分
前章の前者である「高圧的指導」を行ってしまう指導者と話をしますと、驚くほど悪びれておらず、彼らには彼らなりの、以下のような言い分が存在します。
『スポーツ指導では、選手にある程度の精神的ストレスをかけたほうが、その後、強い選手に育つんです』
家庭でのシツケと、好きだから始めたスポーツでの指導と、同列に考えてはいけないのですが、どうしても、コーチたちが選手たち以上に熱を上げやすく、上記のように勘違いをしてしまうようです。
スポーツは”緻密”な指導が大切
ただ、私がスポーツ指導の「コーチング心理学」を多岐に渡って研究している中では、以下のように推奨されてもいるんです。
『学生のスポーツ指導は、とにかく分かりやすく、具体的に、緻密に、教えてあげる必要はある』
これは、大学生などでも、それが必要だそうです。そうなると、小学生は更に、具体的に、分かりやすく、教えてあげる必要がありますね。
だから私は、
『コーチらは、選手たちの練習を、基本見守っていればそれでいい』
とも、やっぱり思わないのです。
高圧的な指導と”緻密”な指導の違い
しかし、『高圧的に、選手たちを追い込むような指導』と、『スキルを緻密に落とし込む指導』とは、全く異なる指導方法です。
前者『高圧的に、選手たちを追い込むような指導』の思想の根底には、
『お前たちがミスをするのは、精神的に弱いからだ。集中が足りないからだ』
という精神論が存在します。
例えば少年野球の指導中、ノックを、ポロっとミスした選手に対して、
『何やってるんだ!下手くそ!こんな球も取れねーでどうするよ!?』
と、コーチが罵声を浴びせる光景は、よくありますよね。
それで、もう1本、ノックを打つと、実際に捕球できたりします。
これは、罵声が正解だったのでしょうか?
よく見ていると、それは誤解なんです。なぜなら、罵声を浴びせられた選手は、次のノックで、
『より、無難にキャッチできる位置、体制でキャッチ』をしています。
もう1歩前に踏み出したほうが素晴らしいプレイであっても、罵声を恐れて、半歩後ろに下がって、ミスしないこと自体を優先してしまうのです。
これは、かなり上手な小学生選手でも、そこそこの選手でも、罵声を浴びせられた直後は、100%決まって、同じ方法を取ってしまっています。
そうではなく、コーチは、ミスのあと、罵声で、無理やり緊張状態を作ろうとするのではなく、どうして、今の捕球方法で、ミスをしてしまったのか、を丁寧に、1球1球、気付かせるコミュニケーションが求められています。
(コーチは当然、ミスの具体的な要因に気付けるだけの、「知識と経験」が求められます。)
スポーツ指導者のたった1つの責務
そもそも、私たちコーチは、選手たちやその保護者から、何を求められているのでしょうか?
それは、たった1つです。
『そのスポーツのスキルを今以上に向上させ、ゲームで通用する選手に育てること』
これだけです。よもや、シツケ教育を、スポーツ指導者に求めませんし、仮に求めている保護者がいたら、それはお門違いも良いところです。
そして、シツケ教育と称したとしても、罵声や体罰、罰則、無駄な連帯責任は、『逆効果』です。
なぜなら・・・『自分が大人に叱られる失敗をしているかどうかは、大人の罵声を合図にすればいい』と、自分で自分の行動を律したり、コントロールしたりする脳が全く育たないからです。
罵声が多く、高圧的指導を当たり前のように行ってしまっているチームは、選手の様子を見れば、すぐ分かります。
試合中、選手たちはほとんど自主的に、選手間で声がけを行っていません。
また、練習中は、1つの練習から次の練習へ移るときに、自主的に、その準備を行う選手は、ほとんどいません。
高圧的指導は、選手たちを精神的に成長させるどころか、むしろ、何でも罵声してもらえるので、赤ちゃん返りのように、自ら考えて行動できるような強い精神力は全く育たず、逆効果なんです。
試合や大会で活躍できる選手とそうでない選手の決定的違い
以前の記事で、「スキル以上にメンタルが重要」であることを執筆しました(こちら)。
試合や大会で活躍できる選手は、『このシーンで、俺(私)は、成功(得点)できる』と自信を持てている選手です。
一方、活躍できない選手は、『俺(私)は、褒められたこともないし、どうせこのシーンでも失敗するだろう』と委縮しており、自信を持てていない選手です。
この違いは、コーチの日頃の指導から生まれています。前者のような選手が多いチームは以下のような傾向があります。
- コーチがめったやたらに選手の行動やアイデアを否定していない
- 指導したことを改善できている選手の行動を褒めている
- ミスをしたとき、精神論ではなく、具体的な身の動きを緻密に指導しており、その具体的な改善を、褒めている
- 長い視点、広い視野で、コーチが選手を見て、接している
一方で、後者のような”自信のない選手”が多いチームは以下のような傾向があります。
- 近視眼的に、選手のささいな行動や試しをダメ出しし、釘を刺している
- ミスをしたとき、罵声を浴びせ、精神論でこじつけようとしている
- 選手に対して日頃から、「馬鹿、下手」などと言ってしまっている
- 試合や大会中、我慢ができず、一挙手一投足に、ダメ出しをしてしまっている
試合中に、叱ったり怒鳴りつけるような行為については、プロ野球の世界でさえ、「そういう時代はもう古い」と警鐘が鳴らされていますね。本日の週刊ポストの記事です
(2019年7月2日『巨人・原監督&阪神・矢野監督の「公開説教」はアリなのか?』/週刊ポスト)
小学生は、自分で環境を選択できない
高圧的指導をしてしまう人が悪びれずに言うことに、
『色んな環境を見れば、そのことが成長に繋がる』
という考え方があります。
これがあてはまるのは、残念ながら、「転職などを自分の意志で出来る大人」です。
小学生や中学生は、「ここはこういう考え方なのか。では、こちらに行ったらどうだろうか」という風には、自ら環境を選択できません。
環境を選択できない、ということは、「目の前の環境は、自分が選んだもの(だから受け入れよう)」と感じるのではなく、
「目の前の環境が、これから味わう世界の全てだ」とすら、感じてしまいかねません。
罵声や、馬鹿にしたり、ミスを罵ったりするような高圧的指導を小学生の時に経験し、かつその環境から逃げられない日々を過ごした選手たちは以下のように世の中を判断するでしょう。
- 男性の大人は、いつも怒鳴るもの(多くの場合、罵声指導は男性)
- 僕の行動はいつも監視され、新しいことを試しても、指摘される
- 世の中は、大人の言う通りに動いていたほうが怒られない
- 大人に指摘された通り、改善したのに、それが適切かどうか、大人はフィードバックしてくれないから、分からない
- 自分を前面に出さないほうが認められやすい
まとめ
上記の通り、高圧的指導をすることで、小学生(中学生も一緒)たち選手の、精神的な強さが育まれることは残念ながら全く無く、むしろ、スポーツにも、それ以外にも、自信を前面に出せず、大人全員に等しく怯え、周りの選手に対して寛容になれず心から応援もできず、チャレンジをできずに、失敗しない、怒られない、無難な選択肢を選ぶ選手(子)に、なってしまいます。
一方で、個々人を受容し、それぞれの考えや行動を尊重するような指導をすることで、選手たちは、失敗を恐れずにチャレンジでき、そして自らに自信を持てて、ここ一番で、実力以上のパワーを発揮し、また、周りの選手に対しても寛容で励まし合える、精神的に強い選手(子)に育っていきます。
執筆:田村恭佑
(人間関係メンター×弁理士×経営コンサル)