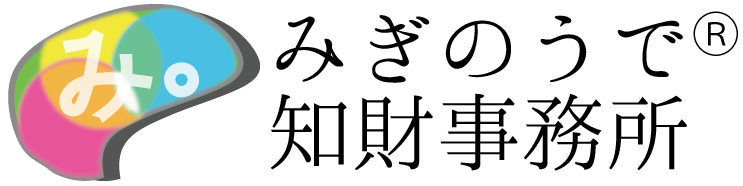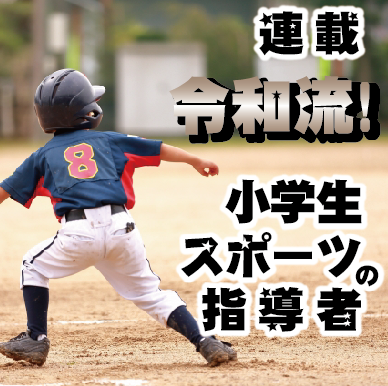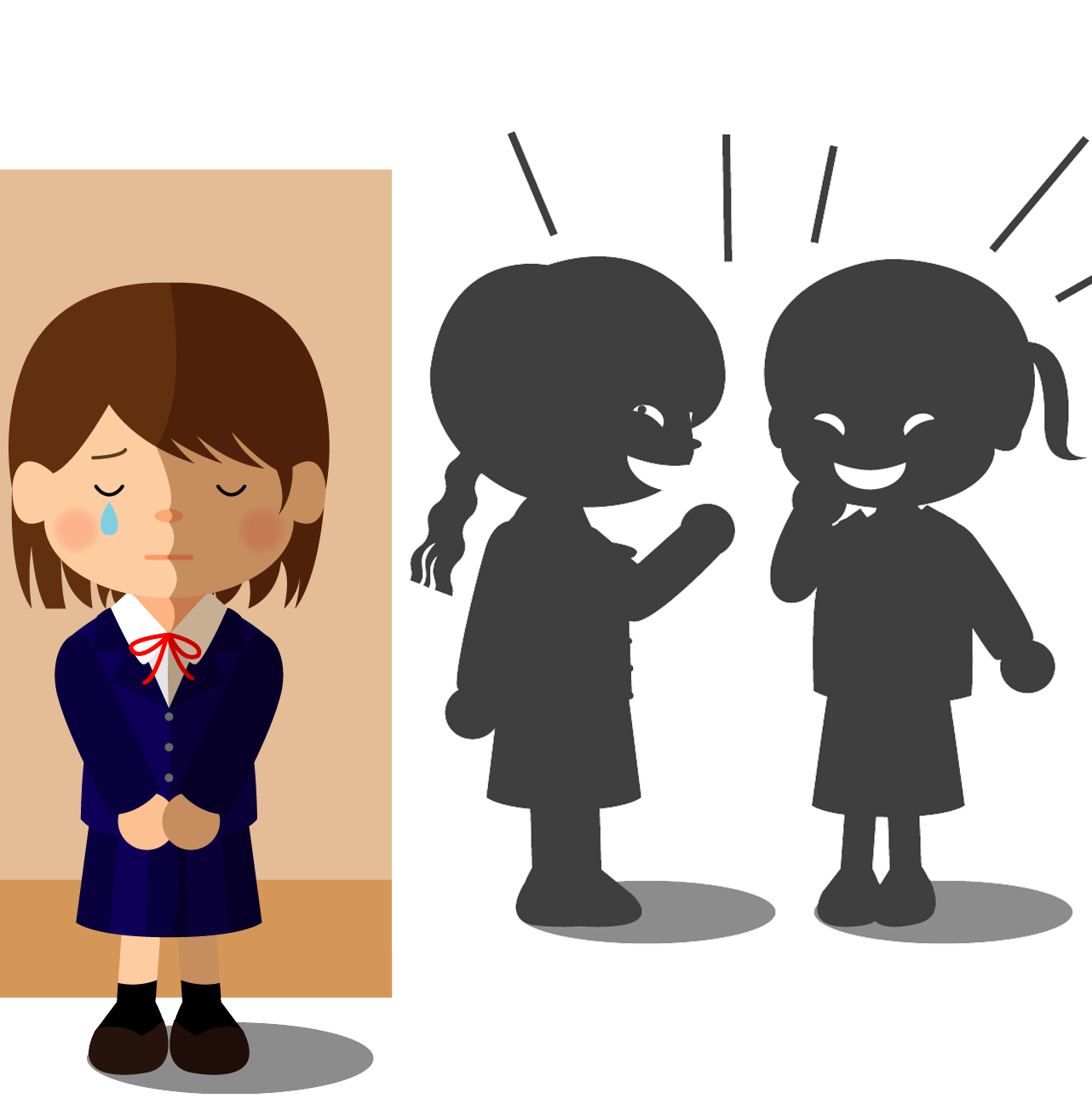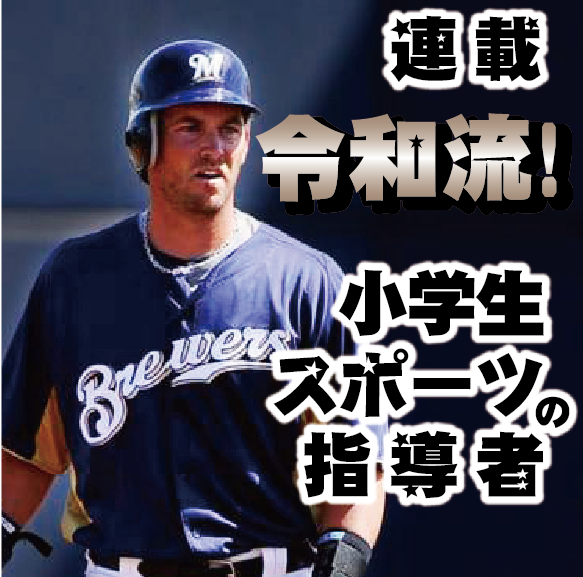本職:経営コンサルタント・弁理士・人材育成・人間関係メンター。
この4月から:少年野球のコーチ。
全ての経験を通じて、現代の『最も理想とする小学生スポーツの指導』について、連載をしたいと考えています。
答えではなく問題提起です。
小学生のスポーツの指導に携わる方々、保護者の皆様に、問題提起をさせていただき、最終的なゴールは、スポーツに取り組む全ての小学生の方々に、健全なスポーツの環境を指導者皆様、保護者皆様と築き上げられたら幸いです。
第1話 『パワハラしないと、強いチームにならないの?』
第2話 『指導者と選手は”対等”と強く意識しよう』
第3話 『メンタルの強さは、技術よりも大切』
今回の第4話は、
『チームと個人。どちらに重きを?』
という内容です。
小学生はどんな動機でスポーツをやっていますか?
昨今は、小学生でも色々なスポーツに取り組んでいると思います。その始めた動機、続けている動機は何でしょうか?
- 将来、そのスポーツでプロとして食べていきたいから?
- 大会で優勝したいから?
- 住んでいる街で一番強いチームになりたいから?
・・・きっとこれらは、「親やコーチ」の描く理想であって、小学生の時点で選手はそんなこと、考えていないですよね。
以下のような動機で始めて、そして続けているのではないでしょうか。
- 友達が楽しそうにやっているから自分も。
- やっている時間が楽しいから。
- うまく出来たとき嬉しいし、親も喜んでくれるから。
- 少しずつ上達を実感し、それが楽しい。
1つ言えることは、
『小学生のチーム員全員が、同じ動機でそのスポーツに取り組んでいるということは、ありえない』
ということですね。
そして、上記からも、小学生が、とっても純粋に、そして様々な動機からそのスポーツに取り組んでいる、ということがお分かりいただけますでしょうか。
試合や大会に負ける。具体的な要因は何でしたか?
そうは言っても、様々な動機の小学生たちを1つのチームとしてまとめるのが指導者の役割の1つですし、また、ただ楽しむだけでそのスポーツに取り組んでいる選手でも、やっぱり試合や大会に、”勝つ”ことは、誰でも嬉しいはずです。
(むしろ指導者は、そのスポーツで”勝つ”ことの楽しさを、早い段階で教えていくことは、上達の近道ですよね)
そこで、やはり、指導者は、試合や大会で、”相手に勝つ”ことも、目指してあげる必要はあります。(試合や大会中に、どういう役割を担うべきか、は第5話以降で、記事にいたします)
指導者は、”勝ち試合”であれば、”どういう要因が組み合わさったから勝てたのか?”を、少しでも再現できる内容で、明確にするといいですね。
また、”負け試合”であれば、”どういう点が相手チームよりも劣っていたのか?”、”どういう要素があれば勝てたのか?”を、これも少しでも再現できる内容で、明確にするといいですね。
負けたとき、以下のような明確化であれば、再現できる形と言えます。
<野球の例>
- そもそもヒットを打てなかった
- 誰かが出塁しても、塁を進めることが出来なかった
- こちらのピッチャーのストライクが、入らなかった
- キャッチャーのパスボールが多く、得点を余計に許した
- 内野ゴロに打ち取っても、エラーが多くアウトを取れなかった
<サッカーの例>
- ドリブルで持ち込むまでは出来たが、シュートで終わる数が少なかった
- 相手がボールを持ったとき、ディフェンスよりも手前、中盤で、プレッシャーをかけられていなかった
- こちらがボールを持っても、パスを受けやすい良い位置にポジショニング出来ていなかった
- みんなで同じ方向にボールを追いかけて、役割分担が出来ていなかった
- キーパーがクリアしたロングボールを、ほとんど相手に取られていた
このように、具体的なスキルであり、かつ、練習で克服できる内容で負け要因を明確化することが、非常に重要です。
やっているよ、と思われるかもしれませんが、多くの指導者が、負け試合のときに以下のような嘆きをしています。これらは、似て非なるものであり、明確化にはなっていません。
- 全然攻撃が繋がらなかったよ
- もっと頭使わないと
- 声が出てないんだもん
- アウト取れないんだもん
- 誰もピッチャー助けてないでしょ
- なんでプレッシャーかけないんだよ
- シュートできるヤツいないのかよ
理想は、自立した個々人の集合体の”チーム”
指導者としては、個々人の指導に加えて、当然、”連携プレイ”や、”チームプレイ”を指導する必要はあります。
つまり、マンツーマンで指導をしてきた選手たちの集合が、翌日の試合や大会で、勝てるか、というと、よほど、個人技が全員組み合わさって、たまたま化学反応でも起こらない限りは、やっぱり勝てないと思います。
ただ、チームづくりの鉄則は、
『選手個々人が最低限、自分の担う役割を担える状態で、その選手たちの集合となっている』
ということです。
野球なら9人、サッカーなら11人、彼らが、実は自分の役割をあまり理解していないけど、『きっと9人(11人)に埋め込めば、薄まるだろう』と指導者が考えてチームを構成してしまうと、たとえその9人11人で勝てても、その勝利には再現性がほとんど見られないし、埋め込まれた選手も何が何だか分からず勝っても、成功体験にも気付きの場にも、なりません。
従って、試合や大会で、”勝ちたい”と思うのは、選手も指導者も当たり前ですが、そのために最優先で必要なのは、
『選手1人1人の、個々人のスキル』
です。
先ほど、”負け試合の具体的な要因”の例を挙げましたが、全て、『1人1人の選手のスキル』です。実は。
だから、連携を覚えさせることも大切ですが、小学生の段階では、とにかく徹底して、個々人の試合で必要なスキルを出来る限り高める指導が、指導者には求められていると考えます。
そうして自立したと言える選手たちの集合体が、初めて”チーム”となります。
練習時間が足りない、というのは嘘
ここまで読まれた指導者のかたは、
『そうなんだけど、個人指導もみっちりして、試合のスキルも身に付けさせて、と色々考えると、練習時間が足りないんだよね』
と、壁にぶつかるかたもいるかもしれません。
小学生は、例えば、もっと磨いたほうがいいスキルが5個あるとしたら、1つだけ、せいぜい2つ、1ヶ月に集中して改善していくのが良いでしょう。
つまり、その1つや2つの、”自宅で出来る自主練”を、強制じゃなく、続けやすい形で、指導者は教えてあげるといいと思います。
自主練は、義務にしてはダメです。(自主練になりません)
しかし指導者は、翌週に、その選手のクセを見れば、ちゃんと自主練を繰り返したのかどうなのか、気付きますよね?気付かないとダメですね。
そういう時に、すっとぼけて、何度も、
『自主練はこういうことをやるといいよ』と、全く同じ指導であっても、繰り返し伝えるといいでしょう。そうすると選手は、
『あぁ、やっぱり同じこと言われるんだから、その自主練がどうしても必要なんだな』
と、理解していくと思います。
責めてはダメです。
<野球で出来る工夫>
個々人のバッティングスキルに課題があれば、徹底して、練習3時間中1.5時間は、バッティング練習でもいいんです。
そういう時に、他の選手は、ポジションについて、集中して守備をしっかりする。そのためには、同時に2列でやるよりも、1列で、1球のゆくえに、集中させたほうが、守備の練習としては効果的だし、バッターにも、具体的な指導をしやすくなります。
後半、守備がダレてきたら、バッターにそのまま進塁してもらったり、「1アウト、ランナー1,2塁!」とか具体的なシーンを設定させたり、紅白戦のように得点を競わせたり、そういう風に工夫すると、たとえバッティング練習が1.5時間であっても、後半も集中が続きます。
(給水は、バッティング練習中に、練習を止めずに給水できるようなローテーションを考えておくといいです。1.5時間ぶっ通しは、実は長すぎます)
<サッカーで出来る工夫>
『相手陣に持ち込んでシュートで終わる』
という攻撃スキルを身に付けさせる個人練であれば、個人戦のようにして、スコアを競わせてもいいですね。その時、ディフェンスも2~3人、味方も1人、バスケの3on3のようにして、選手をローテーションさせれば、守備の練習にも、パスの練習にもなります。ゲーム形式にするなら、その3人全員に、得点が入っても燃えますよね。『ディフェンスなら、5分0点に抑えたら、1点入る』など。
『中盤で相手にプレッシャーをかける』
という守備ススキルを身に付ける個人練でも同様です。主役は今度は守備側になりますが、やはり同様に、3on3のようにして、5分耐えましょう。とかでもいいですよね。これも、ゲーム形式にすると燃えますね。
(間違っても、そのあと、グラウンド1周などの罰が待っている、という懲罰方式は辞めましょう。チームメイトのミスを悪く思うようなネガティブなチームになります)
以上、いかなるスポーツでも、小学生であれば、とにかくチームの構成員であるために、まずは個々人の役割をしっかり理解し、身に付けることが必須です。そのための、練習時間を多く取りましょう。
しかし、個々人の指導というのは、それ以外の選手が、だらけがちなため、攻撃ー守備という関係性をうまく利用して、紅白戦形式なども活用して、飽きさせない工夫を、指導者はしましょう。
執筆:田村恭佑
(人間関係メンター×弁理士×経営コンサル)