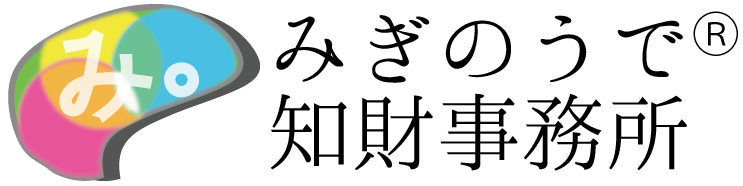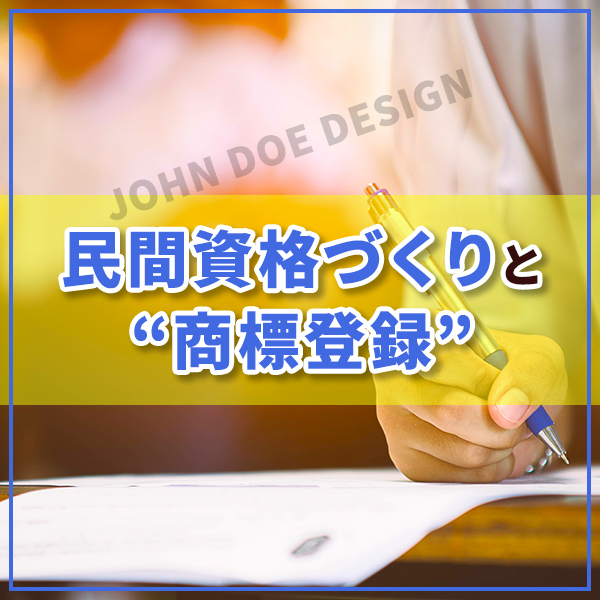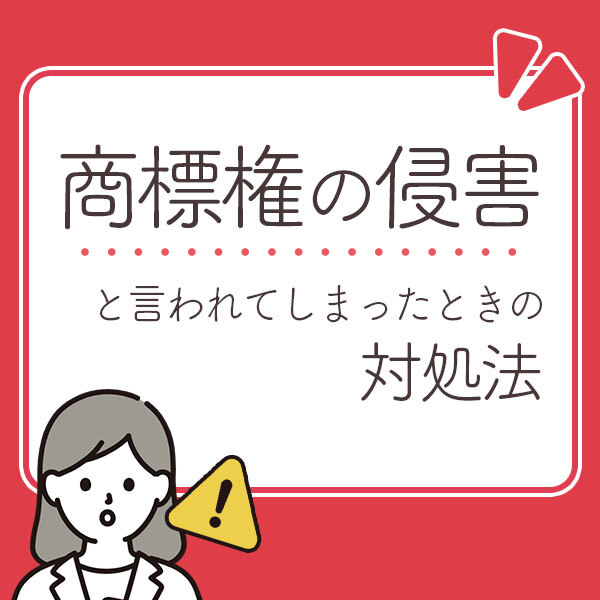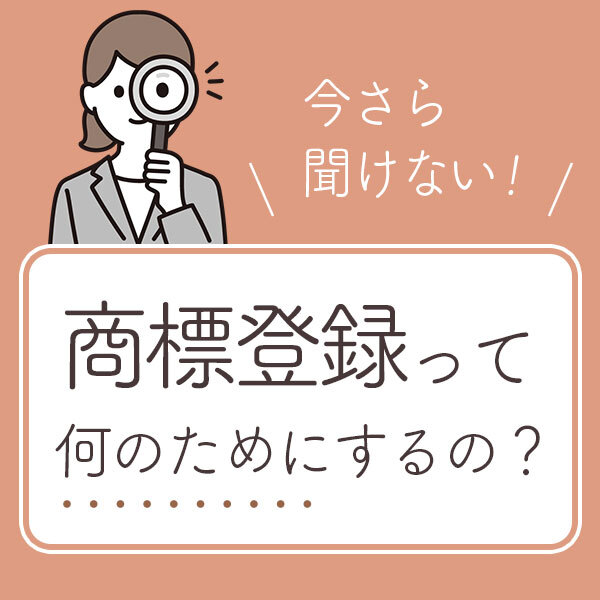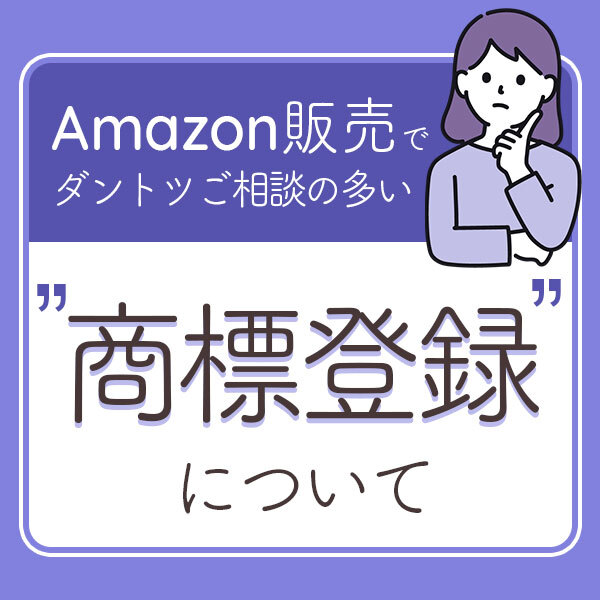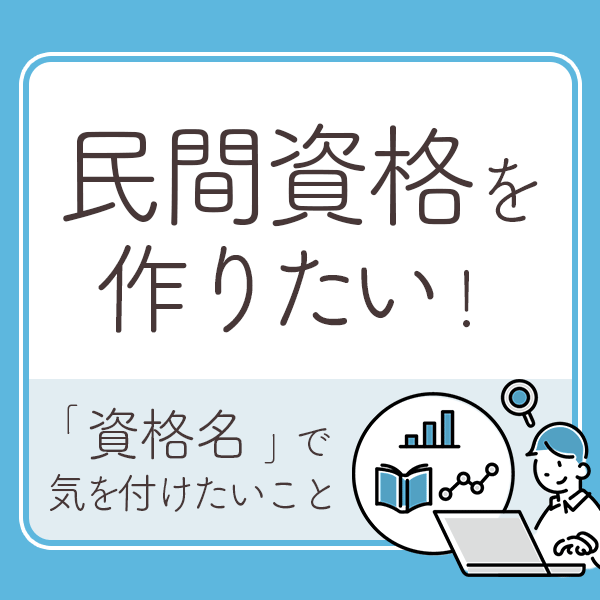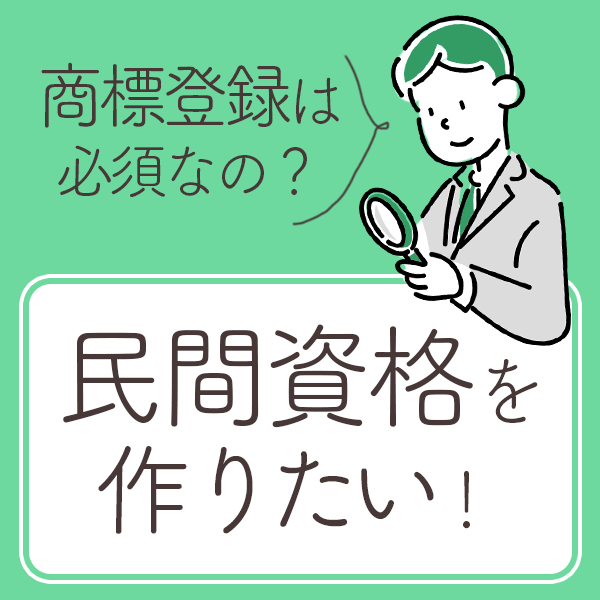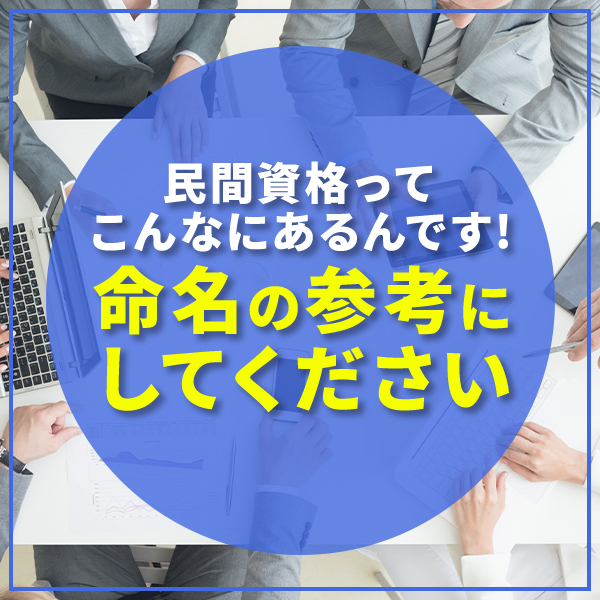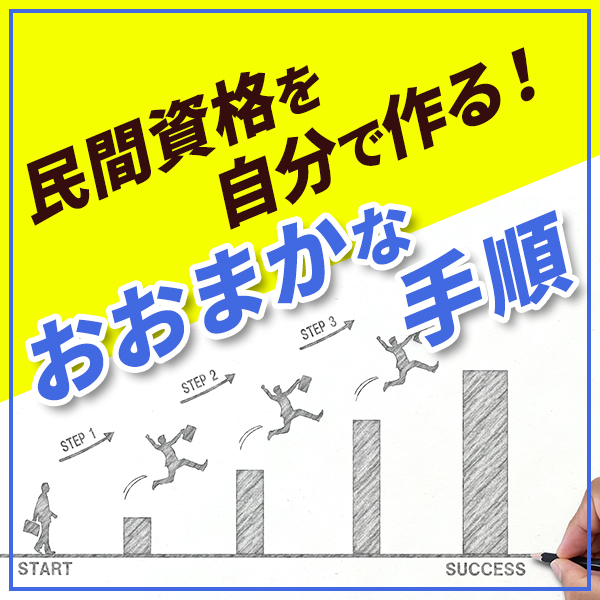こんにちは、弁理士のたむきょん(田村)です。
最近、「民間資格を自分なりに作りたい/設けたい」というご相談を多くいただきます。以下のような記事を執筆していますので、参考になさってください。
【関連記事】民間資格を自分で作る!最も大切な2つのポイント
ご相談をいただく際に、「民間資格を作る際に、商標登録もセットでやりたい」ということを前提としてお考えのかたが多い印象です。
今回の記事では、民間資格づくりにおいて、”商標登録”をする場合としない場合の比較などについて、ご説明できれば幸いです。
目次
“商標登録”をせずに民間資格づくりを成功させる方法
 『私、今度”バレーボール学童コーチ”という民間資格を作りたいんです。商標登録をせずに、この民間資格を成功させることはできますか?』
『私、今度”バレーボール学童コーチ”という民間資格を作りたいんです。商標登録をせずに、この民間資格を成功させることはできますか?』
 『商標登録をせずに、えりなさんが、”バレーボール学童コーチ”という民間資格を成功させることは可能です。でも、かなり遠回りで面倒な手段を取る必要が出てくるので、あまりおすすめはしません。
『商標登録をせずに、えりなさんが、”バレーボール学童コーチ”という民間資格を成功させることは可能です。でも、かなり遠回りで面倒な手段を取る必要が出てくるので、あまりおすすめはしません。
手段とは、”資格に関わる連盟と仲良くなって一員として加わり、資格のための企画をする”ことです。
具体的に流れを解説すると…
まず”学童コーチ”ということは小学生でしょうか、対象とする年代があるかと思います。その年代ごとに、”連盟”というものが必ず存在します(マイナーな競技の場合、ない場合もあります)。
その連盟が明確になったら、以下の手順をとることで、商標登録をせずに、その民間資格を成功させることも、可能と考えます。
- その連盟の理事や委員に自分がなれるように、現在の理事や委員との関係性を築く
- 晴れて理事や委員になれたあと、委員会や会議の場で、”公認コーチ”の設立の必要性をプレゼンテーションし、1~2年かけて、その必要性と必要な要素を、連盟の中ですり合わせする
- その後、民間資格を連盟の中に発足し、自分が資格認定のための講習などを企画し、運営する
』
 『なるほど…少し大変そうですが、こういう方法があることが理解できました。
『なるほど…少し大変そうですが、こういう方法があることが理解できました。
でも…それを1~2年以上かけて、がんばるだけの強い気持ちが、私にあるかどうか…』
 『そうですよね。この方法は“ゼロ”から民間資格を作ろう、というかたにとって、ふさわしい方法ではないんです。
『そうですよね。この方法は“ゼロ”から民間資格を作ろう、というかたにとって、ふさわしい方法ではないんです。
この方法がおすすめなのは例えば、それまで水面下で、5,6人で、”こういう資格が必要ですよね”と、話し合っていて、”いよいよ連盟の中で本格始動していく!”という段階に来ている場合に、取り得る方法ではないかと考えます。』
“商標登録”をせずに民間資格を発足する場合のデメリット
 『連盟や協会などの人脈づくりからスタートするのではなく、個人事業主として、もしくは小さい株式会社として、商標登録をせずに、民間資格を設けることは出来ないでしょうか?』
『連盟や協会などの人脈づくりからスタートするのではなく、個人事業主として、もしくは小さい株式会社として、商標登録をせずに、民間資格を設けることは出来ないでしょうか?』
 『出来ないことはないです。えりなさんがご自身でホームページなどで”バレーボール学童コーチ”資格の説明ページを設けて募集をスタートした瞬間に、商標登録を経ずともその民間資格は発足できます。
『出来ないことはないです。えりなさんがご自身でホームページなどで”バレーボール学童コーチ”資格の説明ページを設けて募集をスタートした瞬間に、商標登録を経ずともその民間資格は発足できます。
でも・・・』
 『でも・・なんですか??』
『でも・・なんですか??』
 『一番最初に説明した”連盟”など、大きな組織の中で民間資格を立ち上げる場合を除いて、ご自身で民間資格を立ち上げる場合に、商標登録を経ないと、いくつかデメリットがあります。
『一番最初に説明した”連盟”など、大きな組織の中で民間資格を立ち上げる場合を除いて、ご自身で民間資格を立ち上げる場合に、商標登録を経ないと、いくつかデメリットがあります。
以下がそのデメリットです。
- 他人が同一か類似の名称で後から商標登録をしてしまった場合、資格名の変更を余儀なくされ得る
- 類似する名称の資格を排除・牽制できないため、受講希望者に対する”差別化”や”ブランディング”が出来ない
- 類似する他人の資格と”差別化”を図るために、広告宣伝などで多大な費用を要する
つまり、民間資格名を商標登録していないと、後から同じ(または類似の)民間資格名で商標登録をする人が現れた瞬間に、民間資格が自分のものではなくなってしまうということです。
あなたが先に使っていた民間資格でも、商標登録をしていないことを理由に「他の民間資格名に変えてください」と訴えられてしまう可能性があります。
商標登録をしていないということは、今後資格が他人に取られてしまうリスクになります。
1~2年かけて、やっと少しずつ世の中に認知され始めた、あなたの資格名を、変更しなければならなくなる。これを考えると大きなデメリットではないでしょうか。』
“商標登録”をした上で民間資格を発足するメリット
 『ということは…小さい規模で、商標登録を経ずに、資格を立ち上げることは、他人の商標権の侵害のリスクを伴うということですね。しかも、広告宣伝などの費用負担も、膨大になる可能性がありますよね。
『ということは…小さい規模で、商標登録を経ずに、資格を立ち上げることは、他人の商標権の侵害のリスクを伴うということですね。しかも、広告宣伝などの費用負担も、膨大になる可能性がありますよね。
それなら、”バレーボール学童コーチ”の資格名を商標登録したいと思いますが、メリットを教えてください。』
 『ご自身で作る民間資格の名称を商標登録する場合のメリットですね!
『ご自身で作る民間資格の名称を商標登録する場合のメリットですね!
(ただし、”バレーボール学童コーチ”では、商標登録は認められません。その理由を後述しますね)
- ご自身が将来、他人から、”その資格名を変更してください”と訴えられる可能性がなくなる
- 商標登録の認められた資格名に、類似する資格名を使用している他団体、他人に”その資格名の使用をやめてください”と、確かな権利をもって主張できる
- 結果的に、他の同様の資格と差別化がラクになり、広告宣伝費などが軽減できる
 『メリットはよく理解できました!
『メリットはよく理解できました!
ではどうして、”バレーボール学童コーチ”での商標登録は、認められないんでしょうか?』
 『それは”バレーボール学童コーチ”という資格名は、”小学生向けバレーボールコーチ”という意味がストレートに名称化したに過ぎないからです。このような名称を特定の人の登録商標としてしまうと、あまりに権利が強くなりすぎてしまうし、正常な取引に支障をきたします。
『それは”バレーボール学童コーチ”という資格名は、”小学生向けバレーボールコーチ”という意味がストレートに名称化したに過ぎないからです。このような名称を特定の人の登録商標としてしまうと、あまりに権利が強くなりすぎてしまうし、正常な取引に支障をきたします。
ですので、多少なりとも、独自性か曖昧性を盛り込んで、資格名を講じてください。
以下の記事は、命名について、参考になるかもしれません。』
【関連記事】民間資格を作る上で、どんな『資格名』にするといい?
 『読んでみます!』
『読んでみます!』
 『当所は、民間資格を立ち上げたい法人様/個人のかた向けに、以下2種のサービスをご提供しています。
『当所は、民間資格を立ち上げたい法人様/個人のかた向けに、以下2種のサービスをご提供しています。
- 民間資格の名称の商標登録のサポート
- 民間資格の立ち上げ自体のご支援
商標登録については、最初の名称の案の調査は無料でご提供し、お見積りを伝えていますので、お気軽にこちらから連絡してください。
』
執筆:田村恭佑
(認知心理学×弁理士×経営コンサル)