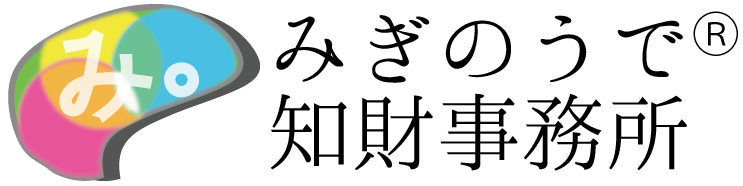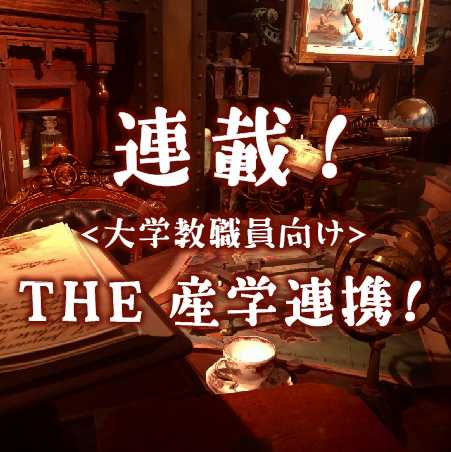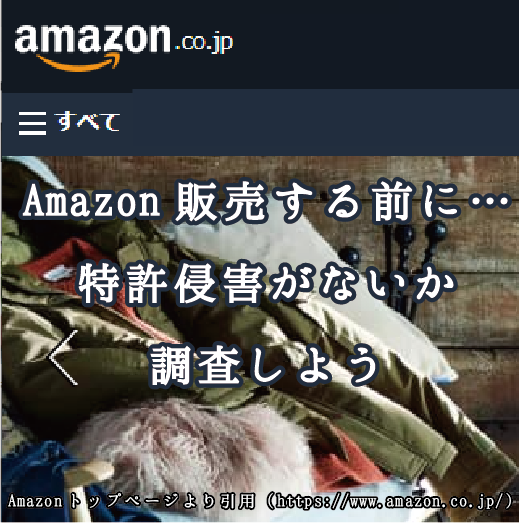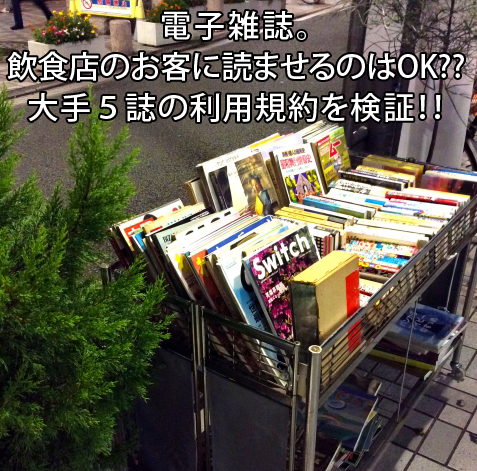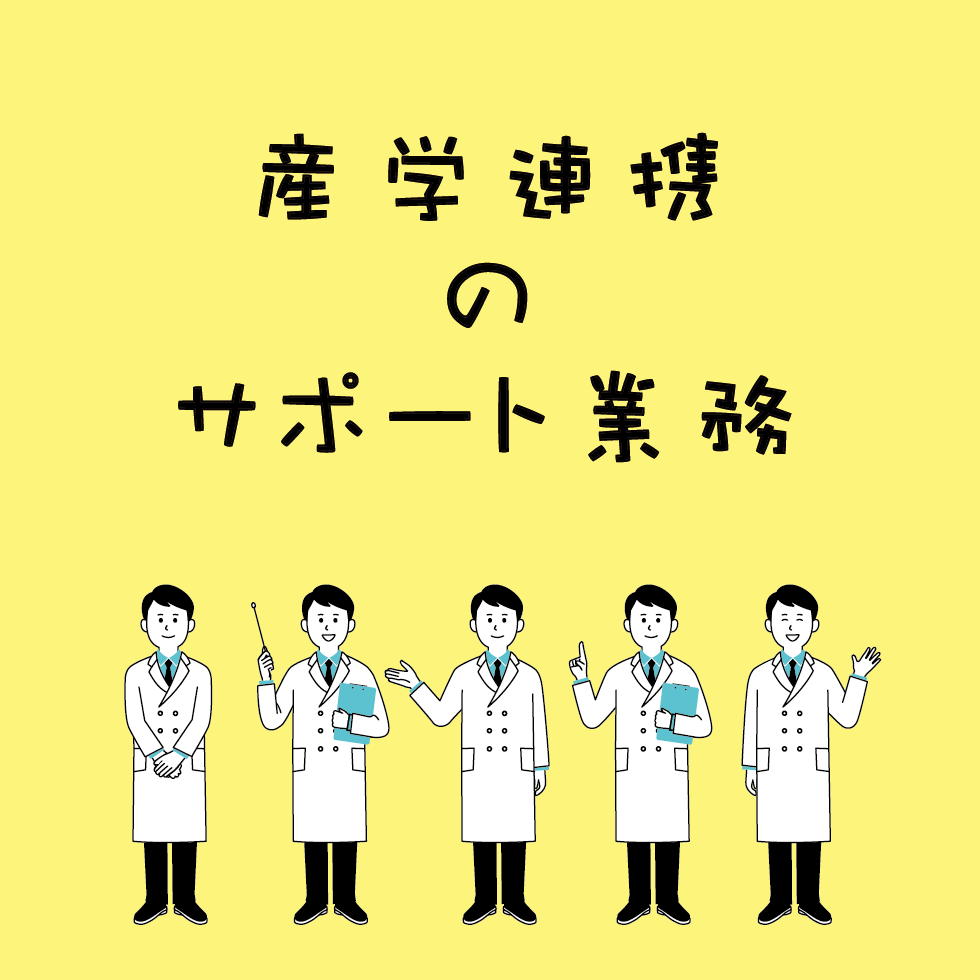私は、約5年間、知的財産と産学連携のマネジメントを大学&研究所の中で担当させていただき、その後、弁理士事務所を経営し、5年経ちます。
大学は、その大学の産学連携の方針や”温度”がマチマチなため、なかなか、情報交換をしあって、適切な産学連携の推進ができる、というわけではない、特有の苦労があります。
そこで、多くの大学様の産学連携の推進のサポートをさせていただいている経験から、少しでも、
『大学の方針の違いがあっても、共通する原理』に値するような情報発信
をできたらと考えています。
『大学教職員向け THE 産学連携!』連載第2回目です。
(この連載でいう『産学連携』とは何か?は、第1回目の記事の冒頭で触れています。こちら)
目次
大学特有の文化…『教員』vs『職員』?!
- ほんの一部の教員が、民間との共同研究などの話題を持ち寄ってくださる
- 産学連携に関心はあるけれど、どのように一歩を踏み出せばいいか分からずにいる教員の方々
- 産学連携に全く関心の無い教員の方々(研究分野により、致し方ない場合も多い)
- 産学連携の課の中で、産学連携の推進やサポートに前向きな職員
- 異動先がたまたま産学連携の課であり、面倒な相談が多いことに、ガードを固めがちな職員
今回の本題ですが、上記の1”産学連携に前向きな教員”と5”事務作業の煩雑さを避けたい職員”は、当然のごとく、”対立構造”になりがちです。
この対立構造こそ、大学が一丸となって産学連携を推進することの、妨げになっていることは、実は非常に多いのが、現状です。』
産学連携の課には、従来に無い相談が寄せられる
『警察犬』のようになってしまうと…?
- 相談『企業と契約を交わさずに、すでに水面下で行っていた共同研究の成果として、発明が生まれた』
対応『過去の契約や条件の約束がないのでは、費用面など、企業と条件の交渉が出来ません。共同で特許出願は難しい』 - 相談『知り合いの経営する会社が、私と共同研究をしたいと言ってくれているが』
対応『知り合い?それは、”利益相反”に当たるんじゃないですか?学内の委員会を通す必要があり、結論まで時間がかかります』 - 相談『企業との共同研究に際して、教育の一環で、学生を参画させたいのだが、可能か』
対応『守秘への誓約書や謝金がないので参画は難しい』 - 相談『自分1人で、発明を創作したが、どうしたらいいか』
対応『予算がない。そして、ご自身で本当に特許性があるか調査をしていないのでは、対応できない』
- (マイナス点)教員が相談を止めてしまった案件の中には、これから大学に収益をもらたす可能性のある案件も埋もれている可能性があります。
それらの機会を失ってしまいます。 - (リスク)本来は、契約を締結した上で民間企業と共同で行うべき研究などについて、都度、相談してくれなくなることで、水面下で、無契約で民間企業と共同で研究を進めてしまい、大学にとっての重要な知財を失うリスクもありますし、気付かずに重要な義務を民間企業に負わされることも、あり得ます。
まとめ
- まず、”産学連携”とは、必ず前例のない要素、事務手続きが煩雑な要素がある、ということをご認識ください
- 次に、教員から相談をされた時に、色々な観点で気付いてしまうこともあると思うのですが、まずは指摘すべき点を探すのではなく、”どうしたら、教員のこの相談を、形に出来るのか”という建設的な議論を、するように心がけましょう
- どうしても、教員のかたにしっかりと理解いただきたい、研究費の執行や期限、事務手続きなどのルールは、とにかく明確に、分かりやすく伝える工夫と努力を、していきましょう。(順番は、あくまで、2の「建設的な議論」が先です)
- 最後に。あなたご自身のイレギュラーな産学連携の案件の対応そのものが、将来に渡って、大学にとって、貴重な前例となり、ノウハウとなります。ぜひ、ノウハウの第一歩を、あなたご自身が作っていきましょう。それも立派な、”知的財産”です
つづく