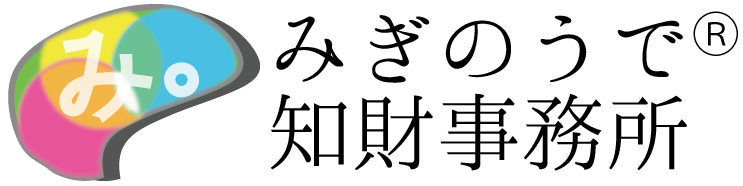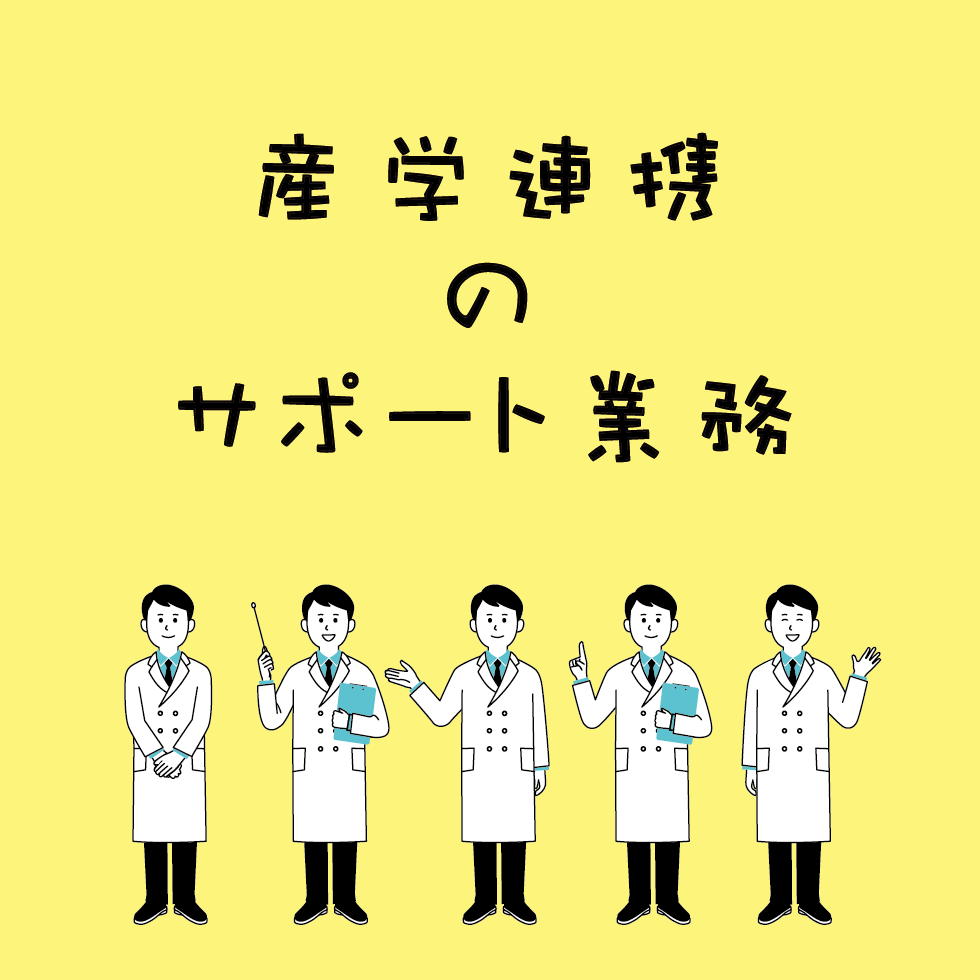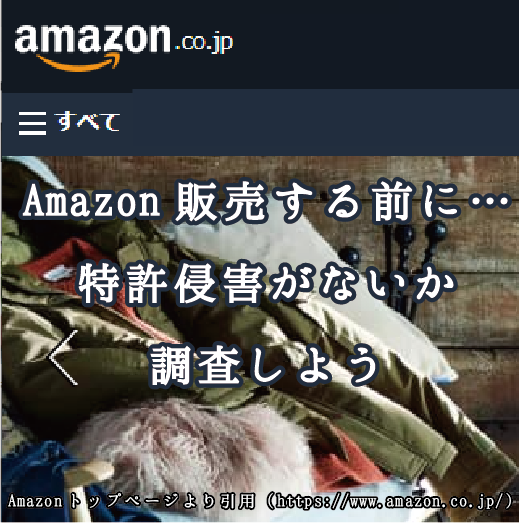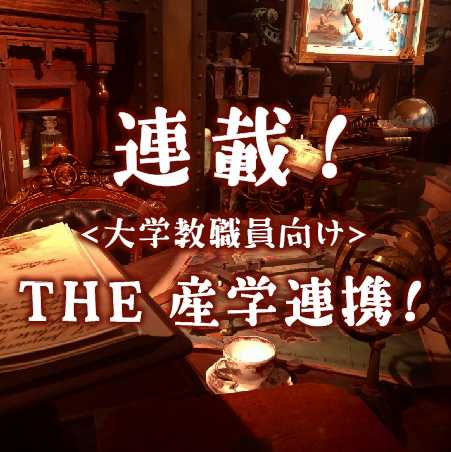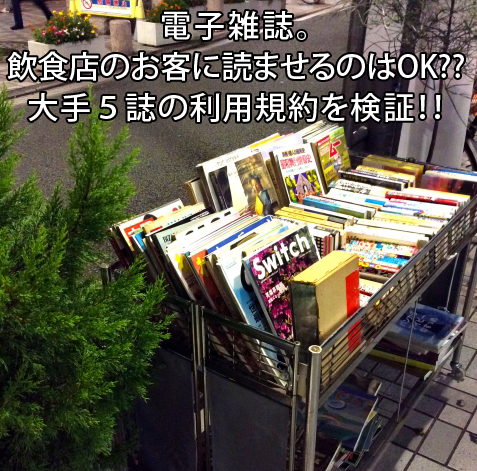当所(みぎのうで知財事務所)では、知的財産を大きく捉えており、主に以下のご依頼をいただいています。
上記のうち、「2~6」は、スポット(個別案件ごと)のご依頼です。
一方、「1」は、「何が発生するか、未定であるが、いつでも細かいことを相談したい」という法人様から、通年でご依頼いただいている業務です。
この1.「知的財産や産学連携の全般的なサポート」は、もともと知財部門と産学連携部門を、法人内で担っていた私から見ますと、便利なサービスではないかと考えています。
この記事で、そのサポート業務について、分かりやすくご説明します。
この記事でいう「産学連携」を簡単に言うと?
「産学連携」は、例えば大学において、「民間の講師を招いて、一緒に、講義をする」ということも産学連携と言います。
しかし、この記事では、
『公的機関、大学、民間などが、自社だけではなく、複数で、共同して、事業をしたり、研究開発をしたりすること』
を指します。具体的には、
- 秘密保持契約のもと、情報交換
- 共同研究契約のもと、共同での研究開発
- 受託事業契約のもと、事業の受委託
- 公的な資金を用いた、事業や研究
などです。
想定している対象
- 大学
- 研究開発を行う機関
- 小規模な企業、ベンチャー
上記が、実際にご依頼をいただいている法人様であり、当所も想定している対象です。
共通点は、
「社内(法人内)に、知的財産と産学連携の、高い専門性を持つ人材を雇用しづらい法人様」
と言えます。もしくは、1人、2人、産学連携の経験者は採用しているが、契約書や知的財産などの重要な判断を自前で全て行うには難しいとお考えの法人様です。
全て”自前”で対処することの難しさ
例えば、当所が、実際に、「知的財産や産学連携の全般的なサポート」のご依頼をいただいている法人様にとって、当所が存在しなかったら、、どのようなリスクや弊害があるか、以下にまとめます。
- 相手法人から提案された契約書の中の、自分たちにとってリスクが大きい条項に気が付きづらい
- 他社との共同研究や共同開発において、事前に、何を定めておく必要があるのか、正確に判断をしづらい
- 共同研究などにおいて、自分たちのリスクは分かっても、どう論理的に相手方に交渉していいか、分からない
- 社内(法人内)で、発明や著作物、ノウハウなどが産まれたのだが、もっとも価値ある状態に発展させる方法が、分からない
- 依頼をした弁護士事務所や特許事務所から、請求書が来たときに、それが妥当な金額か判断できず、今後、もっとコストダウンしたくても、どうコストダウンすればいいか、分からない
上記が、当所が存在しなかったときに、今のお客様に想像される弊害です。
これらは、法人様にとって、知的財産の対応や産学連携の推進を、全て”自前”で行った場合の、弊害となりうると当所は考えています。
他の弁護士・弁理士などとの一般的な比較
当所の代表である田村は、もともと研究開発を主な役割とする機関において、知的財産の対応および産学連携の推進を担っていました。この専門性を持つ弁護士さん、弁理士さんは、非常に稀ではないでしょうか。
一般的に法人対法人の契約書に強い弁護士さんや、交渉力を高く備えた弁護士さんは、当然いらっしゃいます。
しかし、大学や公的機関と、民間との特殊な力関係における契約や、研究の協力体制などに、ピンポイントに力を発揮できる弁護士事務所、特許事務所は、日本中を探しても、なかなか見つけられないのではないかと考えています。
特に、以下に箇条書きする点において、当所だからこそこれらの問題点を解決できると考えます。
- 毎年、産学連携における具体的な問題点を多く対処するため、相場感覚をお伝えしやすく、経験値をそのまま還元できる
- 産学連携における問題対処の経験値(引出し)を、ご相談1つ1つに当てていくことができるため、非常にスピーディに、かつ一般的に安価な金額で対応できる
- 大学・公的機関・民間の、立場や力関係を深く理解しているため、杓子定規な契約書作成などをせず、「落としどころ」や「力の入れ所」をよく理解した上で、契約書を作成したり、修正の相談に応じたりできる
- 産学連携の最大の特徴は、「そこに、発明や知的財産を日々生みだせる研究者が存在する」ということです。もともと研究者の方々と一緒に業務を行っていたため、その研究者の方々との適切な信頼関係を早期に築くことが可能です。
- 必要に応じて、当所が築いている法人様とのネットワークから、問題解決にとって最適な提携先をお繋ぎできます。
本年度に実際ご相談いただいている業務一覧
ここまで読んでくださっている法人の担当者様にとって、具体的に、どういう業務のサポートが考えられるのか、と疑問をお持ちのかたもいらっしゃると想像しています。
そこで、本年度に実際に、年間通じたサポート業務の中でご依頼いただいた案件を、箇条書きします(抜粋です)
- 発明者との面談(発明に該当するか、どう深掘りすればいいか)
- 大学、公的機関、民間の間での二者や三者の共同研究契約書のチェックと修正作成
- 有体物、マテリアル、抗体の有償譲渡、貸与などの契約書作成、相談応対
- 特許などではない、無形の知的財産(調査結果、アイデア、レシピなど)の活用に関する相談応対
- 出版、書籍化に関する著作権についての相談応対
- ハウスマークや個別プロジェクト名の商標取得に関する相談応対
- 発明や著作物の有償でのライセンス(許諾)に関する相談応対
- 知的財産に基づく広報活動に関する相談応対
料金体系
「当社(本学)は、サポート業務は有難くても、それほど、案件が多くない」
とお感じの担当者にとっては、当所ならではの料金設定(後払いデポジット)で、ご納得いただけるのではないでしょうか。
6か月か12か月で、顧客法人様に、予算を設定いただきます。
30万円であったり100万円であったり。
あとは、当所は、ほとんどの相談応対業務は、1件あたり、0.5時間~5時間以内で、対応完了しますので、その予算を「時間予算」に換算して、残額を記録していきます。
当所の2019年度のタイムチャージ(時間単価)は、21600円のため、例えば、4月と5月は、相談が少なく、合計4時間程度しか、業務が発生しなかったら、
予算30万円-(4時間×約2万円)= 残り22万円
ですね。
つまり、相談が多く発生する法人様と、あまり発生しない法人様とでは、その状況にふさわしいご請求しか発生しませんので、あまり相談が多くない法人様にとって、損することはありません。
そして、前払いではなく、6か月後、または12か月後の後払いのため(デポジットとは言いませんね)、例えば、当所の対応能力や、お客様との相性などに、ご不安があっても、あらかじめ、相談いただく”業務量”を一切お約束いただく必要はありません。
※トライアル的に、”スポット(案件ごと)”で、業務をご依頼いただいても構いません。時間単価は、追って量に応じて、ご相談させてください。
最後に
法人様の中に、「知的財産や産学連携の、高い専門性を持つ人材を1名ぐらい、雇用しておこう」と考えた際、だいたい、その1名の人件費は、社会保険を含めると700~1000万円です。
これまで当所は複数の法人様から、年間を通じてのサポート業務をご発注いただいていますが、年間のご請求の最高は、200万円程度(1社当たり)でして、700万円で、どれほどの案件を対応できるか、と言いますと、
700万円÷12か月 = 月間予算58万円
当所の、1案件あたりの実績料金は、1万円~5万円程度
58万円 ÷ 3万円(案件単価) = 19件/月
専門家の対応が必要な案件が19件、というのは、かなり大規模な法人様でない限りは、発生しない量だと存じます。
上記から、700~1000万円で、専門人材をプラス1名、法人内に雇用するのを少し待って、ぜひ、当所にサポート業務としてご依頼いただく、という選択肢も、ご一考いただけないでしょうか。
end