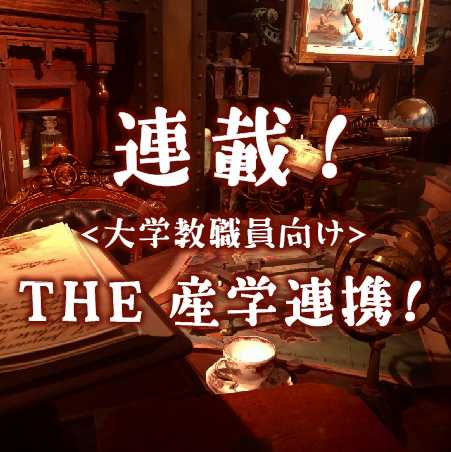
私は、約5年間、知的財産と産学連携のマネジメントを大学&研究所の中で担当させていただき、その後、弁理士事務所を経営し、5年経ちます。
大学は、その大学の産学連携の方針や”温度”がマチマチなため、なかなか、情報交換をしあって、適切な産学連携の推進ができる、というわけではない、特有の苦労があります。
そこで、多くの大学様の産学連携の推進のサポートをさせていただいている経験から、少しでも、
『大学の方針の違いがあっても、共通する原理』に値するような情報発信
をできたらと思います。
『大学教職員向け THE 産学連携!』は、連載にするつもりです。
したがって、1つ1つの記事は、簡潔なものになると存じます。
ご承知おきください。
ここでいう「産学連携」とは?
 『そもそも、産学連携って、何ですか?』
『そもそも、産学連携って、何ですか?』
 『大学の教職員のかた向けの記事なので、大学にとっての産学連携を、説明しますね!
『大学の教職員のかた向けの記事なので、大学にとっての産学連携を、説明しますね!
大きく、以下2つを言うと考えます。』
- 大学講義に、企業のかたも入っていただき、教員と企業の社員とで協力しあって、学生に講義を提供する
- 大学に、企業が市場での開発ニーズなどに基づく研究テーマを提案し、大学教員と、企業の研究者とで、協力して研究を行うこと
※この連載では、省庁や地方自治体からの受託事業や受託研究については対象外とする予定です
 『1.が教育への企業の貢献で、2.は研究への企業の貢献、ということになりますね!』
『1.が教育への企業の貢献で、2.は研究への企業の貢献、ということになりますね!』
 『そうですね。今回の連載では、2.「研究の連携」にスポットを当てて、述べていきます。
『そうですね。今回の連載では、2.「研究の連携」にスポットを当てて、述べていきます。
(最近の「産学連携」に関するニュースや新聞記事でも、2.についてを「産学連携」と呼んでいます)』
企業は、お金になる研究に投資する
 『根本的な質問なのですが、企業は、どうして、大学と連携してまで、研究開発をしたいのでしょうか?』
『根本的な質問なのですが、企業は、どうして、大学と連携してまで、研究開発をしたいのでしょうか?』
 『いいえ、ものすごく重要な質問ですね。そのことを常に念頭に置いていないと、産学連携は、まずうまくいきませんから。
『いいえ、ものすごく重要な質問ですね。そのことを常に念頭に置いていないと、産学連携は、まずうまくいきませんから。
お答えすると、
企業では出来ない研究を、大学は行っているから
です。
企業が研究開発に予算を投じるのは、”事業化”、”商品化”に直結すると見込めるから、ですよね。
しかし、もう少し事業価値や商品価値を深掘りして、根本的な研究から行ったほうが、競合他社と差別化の出来る”新商品”にたどり着ける可能性は、あります。
その点で、大学は、”事業化”や”商品化”に直結するかどうか、で研究を行っているのではなく、あくまで、1つ1つの、教員の専門領域について、損得ではなく、深掘りして、研究を行っています。
企業は、この”深掘りの研究”を、大学と共にしたいから、大学と産学連携するわけですね。』
 『なるほど・・でもやっぱり、企業の研究開発部門は、”事業化”や”商品化”に直結する分野でしか、研究者や研究予算というリソースを、投入しませんよね?』
『なるほど・・でもやっぱり、企業の研究開発部門は、”事業化”や”商品化”に直結する分野でしか、研究者や研究予算というリソースを、投入しませんよね?』
 『その通りですね。
『その通りですね。
企業は、確かに、先生お一人お一人の、マニアックとも言える”深掘りの研究”に関心を持っているのは事実です。
しかし、その”深掘りの研究”が、その企業にとって、お金に繋がる目算がある場合にこそ、企業のリソース(研究者・研究資金)を投じるんです。』
0円でも企業と連携さえできれば良い??
 『それでも、大学と企業の、研究への関心が共通するような場合、企業が一方的に研究費用を出さずに、お互い持ち出しで、共同研究を行うようなケースも、ありますよね?』
『それでも、大学と企業の、研究への関心が共通するような場合、企業が一方的に研究費用を出さずに、お互い持ち出しで、共同研究を行うようなケースも、ありますよね?』
 『もちろん、ありますね。特に、”研究のスコープが定まっていないような段階”に、時々見られます。
『もちろん、ありますね。特に、”研究のスコープが定まっていないような段階”に、時々見られます。
そういうのを大学の産学連携担当の間では、”0円共同研究”と、呼んだりします。』
 『0円共同研究、と言うんですね。このほうが、平等な関係とも考えられませんか?』
『0円共同研究、と言うんですね。このほうが、平等な関係とも考えられませんか?』
 『残念ながら、私はそう思いません。
『残念ながら、私はそう思いません。
そういう初期段階であれば、話は分かります。
しかし、共同研究で、企業も大学も、お互いの役割や研究のスコープが明確になったのであれば、やはり、研究費は、企業側が負担をして、推進がされるべきではないかと思います。
なぜなら・・
共同研究の成果を、大学が商品化する、事業化する、ということは、考えにくいから
です。(国立大学法人法の第22条)
つまり、
企業とのほぼ全ての共同研究は、”その企業の事業に貢献するもの”
となるわけです。』
学内での評価は「その研究で、儲かるのか?」
 『昨今、大学内においては、”産学連携”というのは、推奨されているのでしょうか?』
『昨今、大学内においては、”産学連携”というのは、推奨されているのでしょうか?』
 『大規模な大学においては、学内で推奨しなくても自然と先生方がそういう機会を創出されたりしています。
『大規模な大学においては、学内で推奨しなくても自然と先生方がそういう機会を創出されたりしています。
しかし、中小規模の大学においては、どうしても、大学内部から、”産学連携”を推奨するムードを作っていかないと、先生方が、”産学連携”についても、重要視する、という機運になっていきません。
その点、完全な単科大学を除いて、比較的多くの大学で、”産学連携”の重要性が謳われるようになっているのは、事実です。
ただし、それにも段階があって、おおよそ、以下の順で、大学は産学連携に、深く取り組んでいくようになります。』
- まずは、科研費の採択を増やす、公的な受託研究を獲得する、という動き
- 次に、教育の場面に、企業が持ち込む現場ニーズを取り入れよう、という動き
- 3番目に、企業と共同して、とりあえず情報交換しながら、共同研究をしてみよう、という動き
- 更に発展すると、企業が具体的な開発テーマを持ってきて、大学の教員と、具体的なゴールをイメージしながら共同研究する
 『なるほど~。じゃあ、学内では、基本的には、どんな産学連携も、歓迎されるんですよね?!』
『なるほど~。じゃあ、学内では、基本的には、どんな産学連携も、歓迎されるんですよね?!』
 『もちろん、”全く産学連携しない先生方”よりも、”少しでも産学連携に取り組んでくださる先生方”のほうが、大学にとっては、”新たな可能性を運ぶ先生方”ということで評価はされます。
『もちろん、”全く産学連携しない先生方”よりも、”少しでも産学連携に取り組んでくださる先生方”のほうが、大学にとっては、”新たな可能性を運ぶ先生方”ということで評価はされます。
しかし、5年ぐらい経つと、こういう議論が出てくるんです。
”産学連携のために、課の体制を用意して、先生方の対応に当たっているのに、その産学連携で、いったいいくら儲かってるの?”
と。
つまり、最初のうちは、産学連携しているだけで、頭1つ抜けると言いますか、評価されますが、結局は、特許収入だったり、何かしらのライセンス収入などに結び付かないと、やっぱり、産学連携は、学内で推奨されにくいんです。』
上記を念頭に・・・アクション!
 『そうなんですね・・
『そうなんですね・・
産学連携に、これから真剣に取り組む大学や、今、取り組んではいるけれど、目に見える収入や成果に、結び付いていない、という大学は、どんなアクションを、具体的に起こしていけばいいでしょうか?』
 『非常に素晴らしい質問ですね。
『非常に素晴らしい質問ですね。
詳しくは今後、言及していきますが、私が考える、初期段階の大切なアクションは、以下の通りです。』
【産学連携にご関心のある先生方】
- まずは大学院のときの研究室が一緒だった同窓生などで、近い研究分野に携わっていたかたで、企業に就職されたかたと、コンタクトを取って、情報交換の機会を作る(同窓生に限らず)
- そういう際に、”守秘義務契約”を交わす習慣をお持ちになってください(共同研究の第一歩は、”何かしらの契約を締結すること”とも考えています)
- 0円共同研究でも、まずは、1つ、2つ、面識のできた企業研究者のかたと、共同研究に取り組んでみましょう。その際は、必ず、0円であっても、「共同研究契約書」を締結しましょう。この”締結”も、今後の、研究予算獲得への第一歩になります。
(研究費を出してくれる企業かどうか、というのは、もう少し後で、実績が出来て、付き合い方が分かってから、ゆっくり考えてもいいと存じます)
【産学連携に携わる職員のかた】
- まず課長と相談して、先生方への”啓発”の場を、作っていきましょう。大学にとって推奨する産学連携、契約書の重要性、産学連携の窓口の周知、など
- 実際に、”共同研究をしたいんだけど・・・”と相談に来てくださった先生方に対して、”面倒な相談”と思わずに、”新しい風をもたらす相談”と思って、丁寧に対応をしましょう
- あとは、とにかく、企業の研究者と、何も契約書抜きで、先生が情報交換をしたり、共同で研究をしたりすることのないよう、しっかりと、契約書を締結する、という文化を作っていきましょう。第一歩です。
- いつも、”この研究は、事業化の可能性が高いか”、”収入に繋がる可能性が高いか”という目利きの気持ちを忘れないで、先生方の対応に当たる
つづく