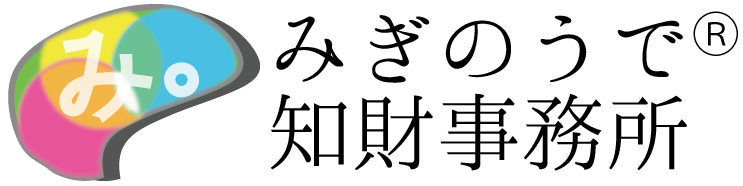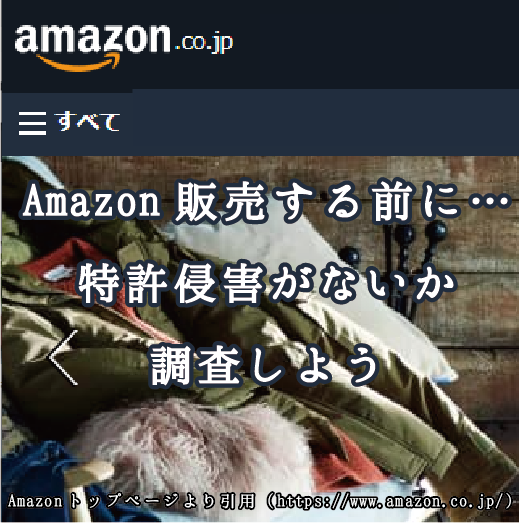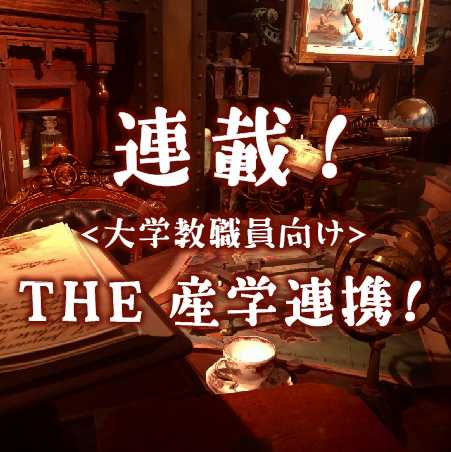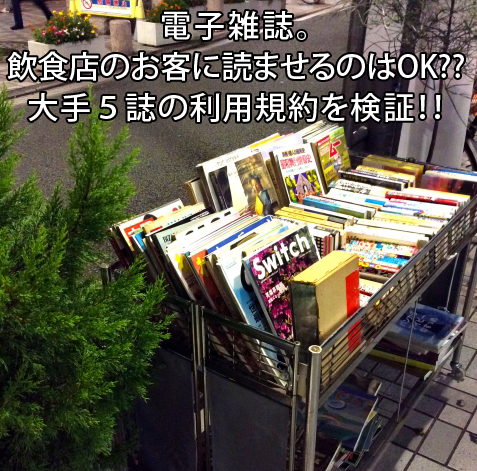2年半前、某有名女性タレントが、奥さんのいる有名ボーカリストと不倫関係に。
そのタレントとボーカリストの間で交わされたLINEの内容が、週刊誌によって全国に暴露されてしまいました。
言わば、情報モラルという観点では、「禁じ手」とされており、今日でもそれは間違いないのですが、様々な動機で、未だに、「個別に受け取った、SNS等の個別メッセージ、メールを、スクリーンショットなどで公開してしまう行為」が後を絶ちません。
今回、『SNSで受け取った、他の人が見ることのできない個別のメッセージを、当該SNS等で公開してしまう行為』について、簡潔に、その良し悪しを記したいと思います。
目次
その行為を単純化して考えると・・?
 『とある誰かが、知人から受けた個別のメールやSNS上のメッセージを、不特定の方々へ公開してしまう、という行為を考えるに当たって、まずどう整理したらいいのでしょうか?』
『とある誰かが、知人から受けた個別のメールやSNS上のメッセージを、不特定の方々へ公開してしまう、という行為を考えるに当たって、まずどう整理したらいいのでしょうか?』
 『SNSやインターネットが普及していない昔から、似たような行為はあったんですよね。単純化して考えることから始めましょう!
『SNSやインターネットが普及していない昔から、似たような行為はあったんですよね。単純化して考えることから始めましょう!
50年前でいえば、例えば、職場でジャイアン部長の悪口を、のび太係員が手紙に書き、封をして、それを、スネ夫係員だけに渡したはずが、翌朝、のび太係員が出勤すると、全社員が見る”社内掲示板”に掲示してしまっていた・・・当然、ジャイアン部長から大目玉を食らうはめに・。
こんなイメージですよね』
例題を設定して考えてみよう。
 『確かにそうですね。悪い行為なような印象はありますね。』
『確かにそうですね。悪い行為なような印象はありますね。』
 『そうだね。それでは、SNSに再び戻して、例題を設定してみましょうか。
『そうだね。それでは、SNSに再び戻して、例題を設定してみましょうか。
- のび太は友人のジャイアンのことで悩みがあり、それをfacebookの個別メッセージ機能で、共通の友人であるスネ夫に相談した
- 相談の際、”誰にも言わないでね”と念を押した
- しかし翌日、スネ夫は、”こんな相談を受けた。ジャイアンは悪くないのに”と、不特定の人が見られる設定で、facebookで、のび太からもらったメッセージのスクリーンショットと共に、公開してしまった
- のび太は、ジャイアンのみならず、他の共通の友達からも一方的に不信感を持たれてしまい、ひどく傷ついた
それでは、上記を例題として、今回の問題を考えてみましょう』
個別メッセージを公開するのは犯罪??
 『そもそも、他人の個別メッセージを、公開してしまう行為は、”犯罪”に当たるのでしょうか?』
『そもそも、他人の個別メッセージを、公開してしまう行為は、”犯罪”に当たるのでしょうか?』
 『大切な視点ですね。”犯罪”と断定するためには、その行為が、”どのような罪に該当するのか”を特定する必要があります。すぐ考えられるのは、名誉毀損、プライバシー侵害でしょうか。
『大切な視点ですね。”犯罪”と断定するためには、その行為が、”どのような罪に該当するのか”を特定する必要があります。すぐ考えられるのは、名誉毀損、プライバシー侵害でしょうか。
これらが成立する要件や、これらが犯罪に該当するのか、を見てみましょう』
『名誉毀損』に該当するか?
 『”名誉毀損罪”という言葉を聞いたことがあるので、これは、犯罪に該当すると思います!』
『”名誉毀損罪”という言葉を聞いたことがあるので、これは、犯罪に該当すると思います!』
 『そうだね。では、”名誉毀損罪”に該当するための”条件”を見てみましょう。
『そうだね。では、”名誉毀損罪”に該当するための”条件”を見てみましょう。
その行為が、”公然と事実を適示(開示)”し、かつ、”人の名誉を毀損”していることが、条件となります。』
(1)公然と事実を適示(開示)
 『”公然”、は、不特定または多数の者が認識しうる状態をいいます。
『”公然”、は、不特定または多数の者が認識しうる状態をいいます。
また、その開示した情報が事実かどうか、は問わないとされています。
ただし、専ら公益目的で開示したのであれば、非該当とされます。
今回のスネ夫の行為は、”公然”に該当し、そして、事実を開示、に該当します。
正義感の下で開示していたとしても、のび太の行為そのものは、「公共の利益を害する」とは言えないため、”専ら公益目的で開示”には該当しません。
*例えば、犯罪や公務員の悪事を秘密裏に知ってしまって、それを告発するような行為が、”専ら公益目的で開示”に該当します。
*スネ夫の行為が、不特定への開示ではなく、最低限の小範囲の社会だけに向けた開示であれば、非該当の可能性はありました。
*スネ夫の行為に、facebookの読者の好奇心を満足させる目的、恨みをはらす目的などが介在している場合、”公益目的”には該当しないと考えられます。
以上から、今回のスネ夫の行為は、”公然と事実を適示(開示)”に該当すると考えられます』
(2)人の名誉を毀損
 『事実の開示により、その人の社会的評価を現に害していなくても、”害する危険”が生じれば該当します。
『事実の開示により、その人の社会的評価を現に害していなくても、”害する危険”が生じれば該当します。
今回のスネ夫の行為により、のび太は、周りから不信感を持たれてしまっているようですし、十分に、のび太の社会的評価を害する危険が見て取れますので、該当します。』
(3)名誉棄損に該当する場合
 『”名誉毀損罪”は、”親告罪”と言って、告訴があって初めて、警察が動きます。
『”名誉毀損罪”は、”親告罪”と言って、告訴があって初めて、警察が動きます。
したがって、のび太が、告訴をすれば、スネ夫は、”名誉毀損罪”で逮捕されます。
(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
一方、告訴まではしなくても、”不法行為”に基づく
- 差し止め請求
- 損害賠償の請求
- 信用回復の措置の請求
のび太はスネ夫に対して、これらが可能です。』
『プライバシー侵害』に該当するか?
 『プライバシー侵害という犯罪はあるのでしょうか?』
『プライバシー侵害という犯罪はあるのでしょうか?』
 『残念ながら、”プライバシー侵害”に”刑事罰”は定められていません。(地方自治体の条例違反の可能性はあり)
『残念ながら、”プライバシー侵害”に”刑事罰”は定められていません。(地方自治体の条例違反の可能性はあり)
もしプライバシー侵害に該当するようであれば、”不法行為”と捉え、民事の争いとして、その行為の差し止め請求と、被った損害の賠償請求、などが可能と言えます。
プライバシー侵害に該当するためには、
- プライバシー情報であること
- 公開・公表した
- 被害者(のび太)の不快・不安を発生させた
上記3つ全てが条件となります』
(1)プライバシー情報であること
 『以下全てを満たした情報が、”プライバシー情報”に該当します。
『以下全てを満たした情報が、”プライバシー情報”に該当します。
- 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる情報
- 一般人が公開を欲しない情報
- 一般の人々にまだ知られていない情報
さて、スネ夫が公開した情報は、のび太の付き合いのある個人であるジャイアンに関する悩みですから、”1.私生活上の事実”に該当します。
そして、のび太も”誰にも言わないで”と注釈していますし、そして、誰でも、特定の個人に対する悩みを、それを打ち明けた相手以外に伝わることを望まないでしょうから、”2.一般人が公開を欲しない情報”に該当します。
さらに、一般の人々にまだ知られていない情報であることは自明でしょう。従って、”3.”にも該当します。
以上から、プライバシー情報の要件は満たすと考えられます』
(2)公開・公表
 『これは言うまでもなく、スネ夫は、facebookで不特定の人向けに公開していますから該当しますね
『これは言うまでもなく、スネ夫は、facebookで不特定の人向けに公開していますから該当しますね
*言葉の定義は、名誉棄損で前述した「公然」の定義と同等と考えられます』
(3)当人の不快・不安を発生
 『のび太は、”ひどく傷ついた”とありますよね。更に、周囲の人から不信感を抱かれてしまったことによる日常生活への不安は甚大なものだと容易に想像できます。
『のび太は、”ひどく傷ついた”とありますよね。更に、周囲の人から不信感を抱かれてしまったことによる日常生活への不安は甚大なものだと容易に想像できます。
従って、”当人の不快・不安を発生”に該当するでしょう』
(4)例外の検討
 『ただし、下記いずれかに該当するようであれば、”不法行為”とならずに、プライバシー侵害行為が適法と認められる可能性があります。
『ただし、下記いずれかに該当するようであれば、”不法行為”とならずに、プライバシー侵害行為が適法と認められる可能性があります。
- 当人の承諾がある場合や、
- プライバシーよりも公共性が重視されるべき事情がある場合、
- 公開の必要性があり、被害者の受けた不利益の程度が低いなど
まず1.ですが、スネ夫は、”誰にも言わないでね”と念押しされていますし、のび太からの承諾は得ていませんでした。
次に2.ですが、のび太は公共に影響を及ぼすような重大な事実をスネ夫に打ち明けている、というよりも、のび太”一個人の感情・感想”を述べているに過ぎず、プライバシーよりも公共性が重視されるべき事情があるとは到底言えません。
最後に3.ですが、上記の通り、”一個人の感想”程度ですから、公開の必要性は当然なく、そして公開により被害者が受ける不利益の程度は、甚大なものです。
上記から、”適法なプライバシー侵害行為”とは言えません』
(5)プライバシー侵害に該当する場合
 『被害者は加害者に対して、
『被害者は加害者に対して、
- 侵害行為の差し止めの請求
- 侵害行為により被った損害の賠償請求
- 場合によっては信用回復の措置の請求
これらの請求ができます』
もし自分のメールが、SNS等で公衆にさらされてしまったら・・・?
 『もし、私のメールが、勝手に公開されてしまった場合、私はどうしたらいいでしょうか?』
『もし、私のメールが、勝手に公開されてしまった場合、私はどうしたらいいでしょうか?』
 『上記の通り、あなたのメールが、”犯罪を示唆しており公共を害する”ような場合でない限り(そんな場合はほとんどありませんが)、公衆にさらした加害者の行為は、立派な、”不法行為”です(名誉毀損に当たれば、立派な犯罪です)
『上記の通り、あなたのメールが、”犯罪を示唆しており公共を害する”ような場合でない限り(そんな場合はほとんどありませんが)、公衆にさらした加害者の行為は、立派な、”不法行為”です(名誉毀損に当たれば、立派な犯罪です)
まずは、当該加害者のあらゆる証拠となる行為を、スクリーンショットなどで保存しましょう。
これは、実物の保存が望ましいです。つまり、そういう事実がある、ということをメモを取るだけでは、不十分と言えます。
その上で、名誉棄損が成立するならば告訴の構えがあること、
プライバシー侵害のみに該当するのであれば、損害賠償請求や信用回復の措置の請求の構えがあることをはっきりと明示した上で、まずは、加害者の行為を「差し止める」警告を通知することが肝要でしょう。
そして、二度と同じことをその加害者が起こさぬよう、毅然とした態度で、賠償金などの請求も検討しましょう(専門家への相談費用なども請求額に含めていいでしょう)。
”いや、行為さえ止めてくれるなら、そこまでオオゴトにはしなくても・・・”とお考えになるなら、”もう二度と公開行為をしないこと”の誓約書などを受け取ることをお薦めします。』
 『SNSの場合、アカウントを削除したりして、加害者が雲隠れするケースも、考えられませんか?』
『SNSの場合、アカウントを削除したりして、加害者が雲隠れするケースも、考えられませんか?』
 『そうですね・・お一人で問題に対峙しようとせず、私どものような身近な専門家に積極的にご相談されるといいと存じます。
『そうですね・・お一人で問題に対峙しようとせず、私どものような身近な専門家に積極的にご相談されるといいと存じます。
また実利が少ないように見受けられますが、”信用回復の措置”と言って、加害者が、自身のfacebook、Twitter上で、今回の行為が自分の完全な落ち度であることを投稿してもらい、被害者の信用を回復するための行動を取ってもらう、というのは、意外と重要なものとなります。専門家としっかりと相談されるといいでしょう。
なお、”あなたのこのような行為は、私の権利侵害(不法行為)に該当しますから、改善が見られない場合は、〇〇のような法的措置や対処策を講じます”という警告を、直接加害者へ行う行為は、いきなり告訴などをするよりも、よほど”大人な対応”のため、この警告が”脅迫”に該当するとは、警察や専門家は判断しません』