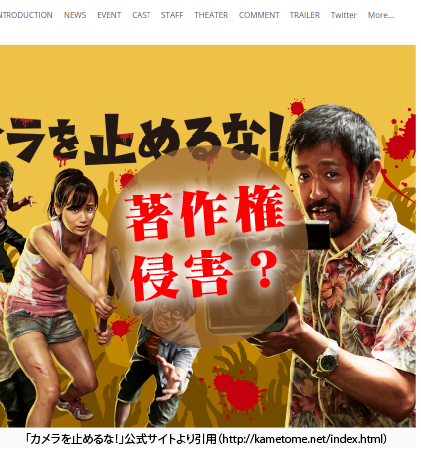
※この記事ではネタバレは一切ありません
こんにちは。日野、八王子、立川ほか多摩エリア(首都圏全域対応)で著作権や商標、契約の仕事を主にしている弁理士の田村(たむきょん)です。
大ヒット映画『カメラを止めるな!』の著作権侵害に関するニュースが先日出ました(こちら)。
今回、原作の実際の内容を存じ上げない中で、私なりにどういう場合に著作権の侵害に当たってしまうのか、侵害に当たる場合どうなってしまうのか、を簡単な記事にいたします。
今回のニュースの概要
 『今回、”カメラを止めるな!”が、舞台作品の著作権を侵害しているんじゃないか、というニュースが出ています。だいたいは、どういう内容なのでしょうか?』
『今回、”カメラを止めるな!”が、舞台作品の著作権を侵害しているんじゃないか、というニュースが出ています。だいたいは、どういう内容なのでしょうか?』
 『いくつかのニュースを読み、だいたいの概要は以下の通りです。
『いくつかのニュースを読み、だいたいの概要は以下の通りです。
- 2011年に、舞台”GHOST IN THE BOX!”が初演。好評につき2013年に再演。2014年に劇団は解散。
(以下、この舞台の作品を”原作”と呼びます)
- 2013年の再演時、”カメラを止めるな!”の映画監督になる上田氏も観劇した事実あり。
(以下、カメラを止めるな!を単に”映画”と呼びます)
- 2015年に上田氏は、原作を演じた劇団員や脚本家に、原作の映画化を打診するが、話は進まず。
- 2016年に映画のプロデューサになる市橋氏が上田氏に映画の制作を打診し、上田氏は前述の劇団員に、原作の映画化を相談。
(その劇団員は原作の著作者・著作権者ではない)
- 映画が完成すると、原作の著作者である和田氏は、上田氏より、和田氏の名前を映画のクレジットに入れたことの事後報告を受ける。
(ニュースに明記されていないが、劇団解散後は、原作の著作権は主宰であった和田氏が持つだろう)
- 和田氏やその代理人の判断によると、映画の構成や設定部分は、原作と類似点が多く、”著作権の侵害”に当たる。
- しかし、映画の監督である上田氏やプロデューサの市橋氏は、原作を”参考にした”ことは認めつつも、侵害の事実は否定。
- 和田氏はこの上田氏らの反応に、訴訟を検討中。』
著作権の侵害に当たる条件
 『なるほど・・・。”カメラを止めるな!”が、”GHOST IN THE BOX!”の著作権の侵害に当たると言えるための条件を教えていただけませんか?』
『なるほど・・・。”カメラを止めるな!”が、”GHOST IN THE BOX!”の著作権の侵害に当たると言えるための条件を教えていただけませんか?』
 『私は両作品の内容を見ていないため、具体的な内容うんぬん抜きで、今回のケースで著作権の侵害に当たってしまう条件について、箇条書きしますね!
『私は両作品の内容を見ていないため、具体的な内容うんぬん抜きで、今回のケースで著作権の侵害に当たってしまう条件について、箇条書きしますね!
- 原作である舞台の脚本やストーリーが、”著作物”に当たること
- 訴えを起こそうとしている和田氏が、原作著作物の”著作権者”に当たること
(著作権者でなくても、著作者として同一性保持の路線で訴えることも可能)
- 映画の脚本及びストーリーに、原作のそれらと類似している部分を含むこと
- 映画の著作権者・著作者が、原作の内容を知った上で、類似していること
- 映画が、すでに上映されていたり、その他何かしらの形になって世に出ていること』
 『この中で、ほぼ、満たすであろう条件はどれでしょうか?』
『この中で、ほぼ、満たすであろう条件はどれでしょうか?』
 『1~5のうち、2、4、5の3つは、おそらく満たします。2は和田氏が、原作の著作権者であること。劇団があるうちは、ひょっとしたら劇団に著作権が帰属していたかもしれませんが、解散したのであれば主宰であった和田氏に著作権が帰属していることは、間違いないのではないでしょうか。
『1~5のうち、2、4、5の3つは、おそらく満たします。2は和田氏が、原作の著作権者であること。劇団があるうちは、ひょっとしたら劇団に著作権が帰属していたかもしれませんが、解散したのであれば主宰であった和田氏に著作権が帰属していることは、間違いないのではないでしょうか。
また、4は、ニュースの中でも、上田氏らが、原作を”参考にした”ことを認めており、また経緯の中でも、何回か劇団の関係者に、原作の映画化を打診しています。これらから4は紛れもなく満たします。
最後に、5は、公開され大ヒットしていますから、もちろん満たします。
今回の問題の争点は、”原作と映画の類似点は、”著作物”に当たるのか?ということかと考えます。』
映画の著作物は、どの要素が著作物なのか?
 『映画や舞台って、全体として著作物、なのは分かるのですが、分解すると、どういう要素は著作物に当たると言えるのでしょうか?』
『映画や舞台って、全体として著作物、なのは分かるのですが、分解すると、どういう要素は著作物に当たると言えるのでしょうか?』
 『明確な決まりは法律では用意されていません。が、著作物は、法律では、”思想または感情を、創作的に表現したもの”と定義されています。(文芸、学術、美術、音楽などに当たるかどうかは、例示に過ぎず重要ではない)
『明確な決まりは法律では用意されていません。が、著作物は、法律では、”思想または感情を、創作的に表現したもの”と定義されています。(文芸、学術、美術、音楽などに当たるかどうかは、例示に過ぎず重要ではない)
この定義に該当するものは全て、著作物に当たると考えて、問題ないでしょう。』
 『脚本、セリフなんかは、思想や感情の”創作的な表現”に当たりそうですね』
『脚本、セリフなんかは、思想や感情の”創作的な表現”に当たりそうですね』
 『その通りだね。脚本というのは著作物と言って間違いありません。だから、脚本上で、類似点が具体的にあれば、それは立派な”著作権の侵害”です。
『その通りだね。脚本というのは著作物と言って間違いありません。だから、脚本上で、類似点が具体的にあれば、それは立派な”著作権の侵害”です。
次に、脚本を、”セリフや動作を列記したもの”と、割り切ったときに、起承転結の作り方、1つのお話の流れや構成、こういうものは、著作物に当たるのでしょうかね?えりなさんはどう思う?
”カメラを止めるな!”は、私は未だ見れていませんが、こういう要素に、多分に観客は価値や面白さを感じているようですよね!』
 『う~ん。脚本家や演出家がそういう起承転結にするのは、まさに、その書いた人の思想や感情が、そうさせていると考えられますよね?! そして、ただそれを、頭の中で考えていた、というのでは、”表現”されていないのでダメかもしれませんが、実際に、”舞台”という形、または、”映画”という、形として”表現”していますから、面白さや独特な感じがあるのであれば、”創作的”であり、やっぱり、起承転結や流れ・構成なんかも、脚本同様、著作物に該当する、と言えるのではないでしょうか・・??』
『う~ん。脚本家や演出家がそういう起承転結にするのは、まさに、その書いた人の思想や感情が、そうさせていると考えられますよね?! そして、ただそれを、頭の中で考えていた、というのでは、”表現”されていないのでダメかもしれませんが、実際に、”舞台”という形、または、”映画”という、形として”表現”していますから、面白さや独特な感じがあるのであれば、”創作的”であり、やっぱり、起承転結や流れ・構成なんかも、脚本同様、著作物に該当する、と言えるのではないでしょうか・・??』
 『私も同感です。脚本と一言でまとめられるのかも、しれませんが、セリフ、演者の動作、話の流れ、起承転結、すなわちストーリー。
『私も同感です。脚本と一言でまとめられるのかも、しれませんが、セリフ、演者の動作、話の流れ、起承転結、すなわちストーリー。
これら全てが、著作物に当たるのでしょう。
(加えて言えば劇中歌とかももちろん著作物ですね)
もし・・・映画”カメラを止めるな!”の、脚本や起承転結のストーリーに、原作”GHOST IN THE BOX!”のそれらとの類似点が客観的に認められるのあれば、残念ながら、”映画(製作者)は原作(製作者)の著作権を侵害している”と言えるのではないでしょうか。』
著作権侵害に当たる場合、どうなってしまうのか・・?
 『侵害かどうか未だ分かりませんが、もし、、映画側が原作の著作権の侵害に当たる場合は、、どうなってしまうのでしょうか?』
『侵害かどうか未だ分かりませんが、もし、、映画側が原作の著作権の侵害に当たる場合は、、どうなってしまうのでしょうか?』
 『まず、映画”カメラを止めるな!”は、舞台”GHOST IN THE BOX!”の、“二次的著作物”に当たる、という関係となり得ます。
『まず、映画”カメラを止めるな!”は、舞台”GHOST IN THE BOX!”の、“二次的著作物”に当たる、という関係となり得ます。
映画と原作が以下のいずれかの関係であれば二次的著作物に当たるでしょう。
- 内面的な形式を維持しつつ、具体的な表現である外面的な形式を変えている
- 原作に脚色して映画が出来ている
- 原作を映画化している
二次的著作物に当たるのであれば、映画側は、原作の著作権を譲り受けるか、または原作側に、正式に”利用許諾(ライセンス)”を受けなければ、映画の公開は出来ません。
(個人的に映画を作り、公開せずに楽しむ程度であれば、著作者の人格権以外の問題は起こりにくい)
つまり、映画側は、原作側の著作権のうち“複製権”、”翻案権”、”上映権”、”頒布権”などを侵害していることになります。
この場合、原作側は、映画側に対して主に以下を、求めることができます。
- 映画の公開の停止を求めること
- 映画の公開に際して失った利益など、損害賠償の請求
- 今後、映画を継続的に公開したり、ブレーレイ販売したりしたい相手に対して、ライセンス料の分配を求める
- 相手が民事上の要求に応じない場合などに、実際は刑事告訴も可能
(著作権侵害の罪は、個人であれば懲役10年以下、または罰金1000万円以下、または両方。法人であれば、3億円以下の罰金)』
 『そうなんですか・・・ただライセンス料を分配するだけ、のような、“大人の解決”が水面下で行われるだけ、というわけにはいかないのですね・・』
『そうなんですか・・・ただライセンス料を分配するだけ、のような、“大人の解決”が水面下で行われるだけ、というわけにはいかないのですね・・』
映画『カメラを止めるな!』が堂々と公開される可能性について
 『映画”カメラを止めるな!”が、堂々と公開できるようになる可能性は、まだあるのでしょうか?』
『映画”カメラを止めるな!”が、堂々と公開できるようになる可能性は、まだあるのでしょうか?』
 『あるとは思います。以下のいずれかに該当するような場合は、映画側は、今後嫌疑を受けることなく、堂々と映画を公開できるのではないでしょうか。
『あるとは思います。以下のいずれかに該当するような場合は、映画側は、今後嫌疑を受けることなく、堂々と映画を公開できるのではないでしょうか。
- 著作権侵害の有無を争うのではなく、映画側は、素直に、原作側の着想の価値を認め、これまでの収益とこれからの収益を、折り合いがつく額で分配する許諾契約を、締結する
- これも侵害の有無は別として、映画側は、原作側から、関連する著作権の譲渡を有償等でしてもらうべく、譲渡契約を締結する
- 侵害の争いを行うのであれば、映画側の本質的な特徴が原作側とは異なるものであり、微細な類似点があっても、著作権の侵害には当たらないと、法廷などでの判断を得る
(ただしこの3.はこれから何年もかかるであろう、イバラの道であり、金銭的な体力も要するし、そもそも1つの映画が注目されるライフサイクルは半年程度と非常に短いため、争っている間にブームが去ってしまう可能性も十分にある)』
 『おっしゃる内容を読むと、著作権の争いというのは、なかなか本当の真実を証明しようとするのには原告側も被告側も、相当な根気と訴訟費用等の財力を要するのですね・・』
『おっしゃる内容を読むと、著作権の争いというのは、なかなか本当の真実を証明しようとするのには原告側も被告側も、相当な根気と訴訟費用等の財力を要するのですね・・』
 『そうだね。今回のケースは、興行収入が相当な額になると報道されているからこその、原作側の踏み切りかもしれません。でなければ、訴訟にかかる費用と得られるであろう収入とを天秤にかけても、泣き寝入りせざるを得ないとも想像します。
『そうだね。今回のケースは、興行収入が相当な額になると報道されているからこその、原作側の踏み切りかもしれません。でなければ、訴訟にかかる費用と得られるであろう収入とを天秤にかけても、泣き寝入りせざるを得ないとも想像します。
やっぱり今回の報道で改めて思うのは、“知的財産を、ゼロから創出した人、会社の価値こそ、尊い。世の中に評価されるべき”ということです。全く後ろめたくなければ、争いに何年かかっても、事実を証明するだけの話ですから。』